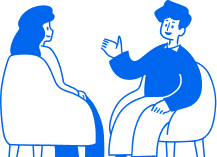「高卒採用を始めることになったけれど、何から手をつければいいかわからない」「大卒採用とどう違うの?」初めて高卒採用を担当する人事の方は、このような不安を抱えていませんか?
高卒採用には、大卒採用とは全く異なる独自のルールと厳格なスケジュールが存在します。これらを理解しないまま進めると、学校からの信頼を失い、採用失敗につながる可能性があります。
この記事では、高卒採用の全体像、最新スケジュール、重要ルール、具体的な手順まで具体的に解説します。高卒採用で悩んでいる方は是非この記事を参考に、スムーズな採用活動の第一歩を踏み出してください。
目次
高卒採用とは?大卒・中途採用との3つの大きな違い
高卒採用を成功させる鍵は、その特殊性を深く理解することにあります。高卒採用の根底には「生徒の学業を最優先する」という大原則があり、この原則を損なわないよう国(厚生労働省・文部科学省など)が定めたルールに基づいて運用されています。
この大原則から、高卒採用は、大卒や中途採用とは異なる次の3つの大きな特徴を持っています。
- 国が定めた厳格な採用スケジュール
- 「一人一社制」などの独自の応募ルール
- 学校やハローワークとの密な連携が必須
1. 国が定めた厳格な採用スケジュール
高卒採用の最大の特徴は、採用スケジュールが国の方針によって厳格に定められている点です。これは、主に厚生労働省と文部科学省が高校側と企業側の双方に対して申し合わせを行っているもので、全企業が遵守義務を負います。
この定められたスケジュールを無視し、フライング行為(規定日前の面接や内定出し)を行うと、その高校からの信頼を一気に失い、翌年以降、求人を受け付けてもらえなくなるなどの厳しいペナルティを受ける可能性があります。
2. 「一人一社制」などの独自の応募ルール
高卒採用には、独特な応募ルールである「一人一社制」が存在します。これは、生徒が応募できる企業を一定期間、一社に限定するというルールです。
このルールは、生徒が学業に集中し、就活に焦らずじっくりと一社に向き合うための学生への配慮から生まれました。法律に基づくものではありませんが、長年にわたり生徒、学校、企業の三者間で守られてきた重要な申し合わせです。
企業はこのルールを前提に、選考計画や職場見学会の日程を立てる必要があります。
3.学校やハローワークとの密な連携が必須
大卒採用との大きな違いとして、高卒採用では、企業が生徒へ直接連絡を取る行為が原則禁止されています。
採用に関する求人票の提出、応募書類の受け渡し、選考の日程調整、合否の連絡など、一切のやり取りは全て、生徒が在籍する学校の進路指導の先生、または管轄のハローワークを通じて行わなければなりません。
そのため、高卒採用の成否は、学校やハローワークと良好な信頼関係を築けるかにかかっています。進路指導の先生方は、企業にとって最も重要なパートナーであると認識しておきましょう。
高卒採用のスケジュールと全体の流れ
高卒採用を成功させるには、定められたスケジュールに沿って計画的に進めることが重要です。ここでは、一般的な高卒採用活動の年間スケジュールと、各時期の企業・高校側の動きを解説します。※地域により異なる場合がありますので、必ず当該都道府県の労働局やハローワークのウェブサイトでご確認ください。
| 企業の動き | 高校・生徒の動き | ||
| 6月 | ハローワークでの求人申込受付開始 | 管轄のハローワークで「高卒求人」の申し込み手続きを行い、求人票を提出 | 期末試験の時期です。先生方は企業からの求人情報を整理し、本格的な進路指導の準備をスタート |
|
7月 |
企業による学校訪問・求人票提出開始 | 7月1日以降、ハローワークから受理された求人票を持って、ターゲットとする高校への挨拶回りを開始。進路指導の先生に自社の魅力を直接伝えるチャンス | 生徒は夏休みに入り、三者面談などを通じて、先生や保護者と相談しながら応募先を具体的に考え始める時期 |
| 8月 | 生徒による職場見学 | 職場見学会を実施。仕事内容だけでなく社内の雰囲気や先輩社員を伝え、入社後のイメージを持ってもらう。 | 生徒は夏休みを利用して職場見学に参加し、応募先を一社に絞り込むための判断材料に |
| 9月 | 応募・推薦開始、選考・採用内定開始 | 9月中旬頃から応募書類の受付を開始。9月16日以降に選考試験を実施し内定者を決定 | 生徒は応募書類を提出し、企業の選考試験に臨む時期 |
| 10月 | 二次募集と 内定者フォロー |
予定採用人数に達しない場合の「二次募集」と、内定者に対する「内定者フォロー」を行う。二次募集は「一人一社制」が緩和され、複数応募が可能になった生徒が対象 | 内定者は入社準備、未内定者は複数応募で就職活動を継続する時期 |
高卒採用で必ず押さえるべき3つの重要ルール
スケジュールと並行して、トラブル防止と信頼関係構築のために独自のルールを正しく理解することが重要です。特に重要な3つのルールについて、その背景とともに詳しく解説します。
ルール1:求人票は必ずハローワーク経由で提出する
高卒採用では、自社サイトなどで直接募集はできず、必ずハローワーク経由で「高卒求人」として求人票を提出する必要があります。
ハローワークから発行される「求人番号」を取得し、その求人票を学校に提出するのが正式な流れです。この仕組みは、生徒を不利益な労働条件から守り、公正な採用機会を確保するためです。
ルール2:地域ごとに異なる「一人一社制」を理解する
生徒が一定期間一社にしか応募できない「一人一社制」は、生徒と企業がじっくり向き合うための重要なルールです。
しかし、法律ではなく慣行であるため、複数応募が解禁されるタイミングや細かな運用は都道府県によって異なる場合があります。トラブルを避けるため、事前に管轄のハローワークや高校の進路指導の先生に確認することが重要です。
「一人一社制」の例外と確認方法
「一人一社制」の運用は全国一律ではありません。一部地域や特定の学科では、当初から複数応募を認めるケースもあります。また、複数応募の解禁日も地域によって差があります。
採用担当者が地域のルールを確認する具体的な方法は以下の2つです。
- 都道府県の労働局やハローワークのウェブサイトで最新の申し合わせを確認する。
- 高校の進路指導の先生に直接尋ねる。
北海道の場合:10月中は「一人一社制」が適用され、11月1日以降は1人2社まで応募・推薦が可能となります。ただし、新規高卒者就職面接会で応募する場合は、期間に関わらず1人2社以上応募することが認められています。(※2026年3月卒業生対象の場合。厚生労働省北海道労働局参照)
ルール3:選考開始日と内定日を必ず守る
特に厳守すべきルールが「選考開始日」(例年9月16日以降)です。この日より前に選考行為や内定を出す「フライング」は絶対にしてはなりません。
フライング行為は学校やハローワークからの信頼を著しく損ない、翌年以降の求人を受け付けてもらえなくなるなどの厳しいペナルティにつながる可能性があります。法令遵守を徹底してください。
【失敗しない】高卒採用の具体的な手順を7ステップで解説
これまでの情報を踏まえ、実際に高卒採用を進めるための具体的な手順を7つのステップで解説します。この流れに沿って進めれば、初めてでもスムーズに採用活動を行えます。
- 採用計画の策定とターゲット設定
- ハローワークへの求人申込と求人票の作成
- 高校への挨拶・求人票の送付
- 職場見学の受け入れ準備と実施
- 応募書類の受付と選考(筆記試験・面接)
- 内定通知と入社手続き
- 内定者フォローと入社後研修
ステップ1:採用計画の策定とターゲット設定
最初のステップとして、「どのような人材を、何名、いつまでに採用したいか」という採用計画を明確にすることが重要です。
求める人物像を定義した上で、ターゲットとなる人材がいそうな高校(例:製造業なら工業高校)をリストアップし、過去の実績や学校の所在地なども考慮してターゲットを絞り込みます。
ステップ2:ハローワークへの求人申込と求人票の作成
6月1日以降にハローワークで求人申し込みを行います。求人票は「会社の顔」です。条件面だけでなく、「仕事内容」「成長性」「働く先輩の様子」などを高校生に分かりやすい言葉で具体的に書きましょう。
専門用語を避け、写真やイラストを活用するなどの工夫も有効です。
ステップ3:高校への挨拶・求人票の送付
7月1日以降に高校への挨拶回りを行います。アポイントメントを取り、進路指導の先生に直接求人票を手渡しするのが最も丁寧な方法です。
訪問時に、求人票では伝わらない魅力を補足するパンフレットなどを持参すると効果的です。先生に「安心して生徒を送り出せる」と思ってもらうことが信頼関係の第一歩です。
ステップ4:職場見学の受け入れ準備と実施
夏休み期間中に実施される「職場見学」は非常に重要です。単なる社内案内ではなく、仕事の面白さややりがいを体感できるプログラム(作業体験、先輩社員との座談会など)を企画しましょう。
生徒の不安を解消し、親近感を持ってもらうことが目的です。見学後、学校経由で丁寧なお礼状を送るなどのフォローも心がけてください。
ステップ5:応募書類の受付と選考(筆記試験・面接)
9月以降の選考プロセスでは、筆記試験と面接の組み合わせが一般的です。高校生との面接では、学業以外の経験(アルバイト、部活動)に関する質問で人柄やポテンシャルを見極め、「なぜこの仕事に?」「入社後の挑戦」など、前向きな意欲を引き出す質問を心がけましょう。
ステップ6:内定通知と入社手続き
内定決定後、まず学校の先生を通じて速やかに内定連絡を行い、その後、本人宛に正式な「採用内定通知書」を送付します。保護者にも安心してもらえるよう、会社の概要や待遇、研修制度などを記載した書類を同封すると、より丁寧な印象を与えられます。
入社承諾書など、必要書類についても分かりやすく案内することを徹底してください。
ステップ7:内定者フォローと入社後研修
最後のステップとして、内定を出してから入社までの「内定者フォロー」が重要です。内定者の不安を取り除き、入社意欲を維持するためのフォローが、内定辞退や早期離職の防止に繋がります。
具体的なフォロー施策として、社内報の送付、内定者懇親会、先輩社員との交流会などがあります。入社後は社会人としての基礎を学ぶ研修を実施し、スムーズなスタートをサポートすることが大切です。
高卒採用を成功に導く5つのポイント・注意点
これまでの手順やルールを踏まえた上で、採用活動をさらに成功させるための5つのポイントと注意点を解説します。これらの点を押さえることで、他社との差別化が図れます。
- 進路指導の先生との信頼関係を築く
- 高校生に伝わる言葉で自社の魅力を伝える
- ミスマッチを防ぐため、正直な情報提供を心がける
- 保護者の視点を意識した情報発信を行う
- 二次募集の可能性も視野に入れておく
1.進路指導の先生との信頼関係を築く
この記事の中で何度も伝えていますが、成功のポイントは、進路指導の先生との信頼関係構築にあります。一度きりの訪問で終わらせず、定期的な連絡や近況報告など、継続的なコミュニケーションを心がけてください。先生との信頼関係が、翌年以降の安定した採用に繋がる可能性が高まります。
2.高校生に伝わる言葉で自社の魅力を伝える
専門用語を避け、高校生の目線に立った分かりやすい言葉で魅力を伝えることが重要です。事業の将来性といった難しい話よりも、「自分の生活との関わり」「身につくスキル」「成長のイメージ」といった身近な情報が響きやすいです。
例えば、「スマートフォンの部品を作っている」「3年目の先輩が大きなプロジェクトを任されている」のように、働くことの楽しさややりがいを伝える視点が大切です。
3.ミスマッチを防ぐため、正直な情報提供を心がける
早期離職の原因となるミスマッチを防ぐため、会社の良い面だけでなく、仕事の厳しさや大変な部分も正直に伝える誠実さが重要です。
悪い面を伝える際は、「大変だけど、やり遂げた時の達成感は格別」のように、ポジティブな側面とセットで伝えることで、生徒が入社後の働き方を具体的にイメージし、覚悟を持って入社を決められるでしょう。
4.保護者の視点を意識した情報発信を行う
高校生の就職活動に大きな影響を与える「保護者」の視点を意識することが重要です。保護者が抱きがちな不安(「本当に大丈夫な会社か」「将来性はあるか」)に寄り添う情報発信が必要です。
具体的には、パンフレットに福利厚生や研修制度、育休取得実績などを明記したり、職場見学の際に保護者向け説明会を開いたりすることを提案します。
5.二次募集の可能性も視野に入れておく
一次選考で計画通りの人数を採用できるとは限らないため、二次募集の可能性もあらかじめ想定しておくことが重要です。内定辞退の可能性も考慮に入れましょう。
具体的な二次募集の動き方として、10月以降に複数応募が可能になった生徒を対象に、ハローワーク経由で追加情報を発信したり、一次募集で接点のあった高校に再度アプローチしたりする方法が有効です。
まとめ:高卒採用の成功はルール理解と計画的な準備から
高卒採用は独自のルールを持つ複雑なものであることを改めて述べましたが、その背景には「高校生を守り育てる」という大切な目的があります。
高卒採用を成功させる鍵は、この記事で解説したスケジュールや手順、成功のポイントを理解し、計画的に準備を進めることです。
特に重要な成功要因として、「スケジュールの厳守」「学校の先生との信頼関係構築」「生徒と保護者への正直な情報提供」の3点を忘れずに、高卒採用に取り組んでみてください。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。