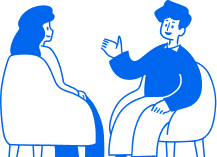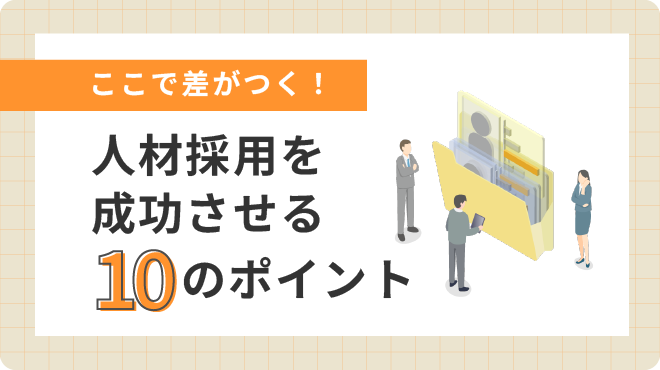
採用は企業にとって最も重要な活動と言っても過言ではありません。企業の持続的な成長には、優秀な人材の確保が不可欠です。しかし、近年の採用市場では人材獲得競争が激化しており、どのように採用活動を進めれば良いか頭を悩ませている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、採用を成功させるための10のポイントや、代表的な採用手法などを解説します。「初めて採用担当をまかされた!」という方も、ベテランの人事担当者の方も、人材採用の基礎についてご紹介しますので、ぜひ今一度チェックしてみてください。
人材採用が難しい3つの理由
はじめに、近年の人材採用が難しい背景として、3つの理由を解説します。これらの理由を理解することで、どのような採用戦略が有効か考えやすくなります。
生産年齢人口が減少している
生産年齢人口とは15~64歳の人口であり、働き手の中核です。少子高齢化に伴い、日本の生産年齢人口は年々減り続けています。総務省統計局の「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)」によると、2024年10月1日時点の生産年齢人口は7,372万8千人で、前年比で22万4千人の減少となりました。
特に北海道では、2013年から2023年の10年間で生産年齢人口が約13%(45万人以上)減少しており、全国的に見ても深刻な状況です。
生産年齢人口の減少により、企業が採用できる人材の母数そのものが少なくなっているのが現状です。さらに加えて北海道では若者の道外流出も顕著であり、このことから特に中小企業は、人材獲得競争は厳しい傾向にあります。そのため従来通りの採用手法だけでは、人材の確保は困難な局面を迎えています。
採用コストは上昇傾向
採用コストとは、企業が人材を獲得するために必要な総費用のことで、大きく二つの要素に分類されます。一つは、求人広告費や人材紹介手数料など、外部のサービスに支払う「外部コスト」です。もう一つは、採用担当者の人件費や面接会場の費用、応募者の交通費など、社内で発生する「内部コスト」です 。
厚生労働省の「雇用動向調査」によると、2022年、2023年と、入職者数が離職者数を上回る「入職超過」の状態が2年連続で継続。特に2023年には入職超過率が前年比0.8ポイント拡大して1.0ポイントとなりました 。これは日本の労働市場が「超売り手市場」であることを明確に示しています。
さらに全体では入職超過の状態ですが、雇用形態別にみてみると正社員では、2022年に離職者数が入職者数を約16.6千人上回る「離職超過」となっており、正社員層を巡る人材獲得競争が特に熾烈であることがわかります。一方で、パート・アルバイトは、2022年には入職超過が約157.9千人と増加傾向が顕著となっています。
労働市場全体の人手不足に加え、特に正社員採用において、労働者の流動化と他社からの引き抜きが活発化している市場構造に企業は直面しています。こういった転職市場の活性化により、企業間の賃金上昇競争と高コストな人材紹介サービスへの依存度が増し、それが採用コスト全体を押し上げています。
企業は、労働市場の需給逼迫によって、求人活動費という「外部コスト」だけでなく、獲得後の人件費という「内部コスト」の両方を押し上げられるという課題に直面しているのです。
ミスマッチが発生する可能性がある
応募者を採用しても、入社後に早期離職された経験は人事担当者の方であれば誰しも経験があるのではないでしょうか。企業が求めるスキルや価値観と、求職者が望む仕事内容や社風が合わない状態が発生すると早期離職に繋がってしまいます。
ミスマッチによる早期離職は、採用にかけた時間やコストが無駄になるだけでなく、社内の士気低下を招く恐れもあります。ミスマッチを防ぐには、企業が求める人物像を採用活動の中できちんと伝えることが大切です。
代表的な人材採用の手法5選
人材採用に関わるサービスは、従来どおりの手法から時代とともに新しいサービスまで様々なものが出てきています。自社に合った採用手法を取り入れるとともに時代に合ったさまざまな方法を試すことも大切です。ここからは、人材採用の代表的な手法を5つ紹介します。
1.求人サイトの活用
求人サイトは、幅広い求職者層に自社の求人情報を届けられる、ポピュラーな採用手法です。多くの求職者の目に触れるメリットがある一方、多数の求人に埋もれやすいため、ターゲットに響く魅力的な求人原稿の作成が必要になります。また、「掲載料金が安い」「特定の業界に強い」など、求人サイトの特徴もさまざまで、複数のサイトを比較検討し、自社に合ったものを選ぶことが大切です。
2.転職エージェントの活用
転職エージェントは、企業の採用要件に合致する人材を、専門のコンサルタントが探し出して紹介してくれるサービスです。キャリアアドバイザーが事前に候補者のスクリーニングを行うため、より求める人物像と近い候補者との面接に集中できます。採用が決定した時点で紹介手数料が発生する「成功報酬型」が主流で、求人掲載などにかかる初期費用が抑えられる点がメリットです。転職エージェントにも「中核人材に強い」「地元志向な人材が多い」「特定業界の人材が多い」といった独自の特徴があるため、複数を比較検討したうえで利用することをおすすめします。
3.ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者を探し、直接アプローチを行う手法です。転職サイトのスカウト機能を利用し、自社が求める人材に直接スカウトメールを送ります。今すぐの転職を考えていない「転職潜在層」にもアプローチできる点がメリットです。候補者一人ひとりに合わせたアプローチが必要で手間はかかりますが、採用のミスマッチを減らし、採用コストを抑えやすい傾向があります。
4.リファラル採用
リファラル採用は、自社の社員に友人や知人などを紹介してもらうことで、採用につなげる手法です。紹介者である社員を通じて、企業の文化や仕事内容についてリアルな情報が伝わっているため、入社後の定着率が高い傾向にあります。求人広告費や紹介手数料がかからず、採用コストを大幅に削減できる点も大きな魅力です。制度を成功させるには、社員が「知人にも勧めたい」と思えるような職場環境の整備や、紹介者へのインセンティブを検討することが重要です。
5.アルムナイ採用
アルムナイ採用とは、一度退職した元社員を再雇用する手法です。元社員であるため、企業文化や事業内容への理解が深く、入社後すぐに活躍できる即戦力が期待できます。他社で培った新たなスキルや経験を還元してくれるメリットもあります。しかし、退職者によっては既存社員から反対意見が上がる可能性があり、既存社員との交渉を慎重に進める必要があります。
効果的な人材採用を行う10のポイント
ここからは、効果的な人材採用を行うポイントを10個にわけて解説します。各ポイントを一つひとつ実践することで、自社にマッチした優秀な人材を採用できる可能性が高まります。
1.採用したい人物像を明確化する
採用したい人物像を明確にすると、求人情報で訴求すべき内容や面接での質問の精度が上がり、ミスマッチの防止につながります。どのようなスキルや経験を持ち、どのような価値観を持つ人材が会社の成長に貢献してくれるのかを考えて、募集の際に伝えましょう。求める人物像を考える際は、現場の管理職や社員の意見をヒアリングすると効果的です。「〇〇の業務経験を活かして、△△の課題を解決してほしい」というレベルまで具体化しましょう。
2.採用業務の効率化を意識する
人材を採用するにあたって、さまざまなプロセスを踏む必要があります。例えば、会社説明会、書類選考、適性検査、面接などです。このプロセスが多すぎると、採用担当者の業務が煩雑になり、応募者一人ひとりを正確に見極めにくくなります。また、応募者にとってもハードルが高くなりがちです。
「会社の説明は面接内でできないか」「面接の回数が多すぎないか」など、プロセスを再確認し、採用活動を効率良く進められないか検討しましょう。採用担当者の業務コストを軽減するという点では、採用管理システムを導入して応募者情報を一元管理するのも有効です。
3.労働環境や待遇の改善に努める
労働時間が長すぎたり、業務内容の割に給与が低かったりする会社は、応募者に魅力的に映りにくいです。採用活動を行うにあたって、客観的に自社の現状を分析し、競合他社と比較して見劣りする点があれば改善に努める必要があります。業務効率の改善による残業時間の削減や有給休暇の取得の奨励を進めて、働きやすい環境づくりを意識しましょう。資格取得支援制度や社員旅行など、福利厚生を充実させるのも効果的です。
4.働き方の多様化を検討する
現代では、リモートワークやフレックスタイム制度、時短勤務など、個々のライフスタイルに合わせた働き方を望む人が増えています。多様な働き方ができる企業は、画一的な働き方のみの企業より魅力的に映りやすいです。また、育児や介護と仕事を両立したい優秀な人材や、通勤圏外に住む人材も採用対象にできます。採用できる人の幅を広げるためにも、柔軟な働き方の導入も検討してみましょう。
5.SNSを活用して情報発信を行う
SNSを活用して、普段から社員のインタビュー・日常のオフィスの様子・社内イベントなどを発信すると、会社のリアルな雰囲気が伝わりやすいです。採用活動の際にSNSも参照してもらうことで、求職者に社風を伝えやすくなり、ミスマッチの可能性を減らせます。求職者との直接的なコミュニケーションも可能で、企業のファンを増やし、将来の応募者候補を育てることにもつながります。
6.求職者に選ばれているという意識を持つ
採用活動をしていると「自分たちが応募者を選んでいる」という意識が強くなりがちです。しかし、売り手市場においては「求職者が会社を選ぶ」という側面が強いです。優秀な求職者ほど、複数の企業から内定を得ており、比較検討していることが多いでしょう。面接での高圧的な態度や、選考結果の連絡が遅れるといった不誠実な対応は、企業の評判を損なう原因になります。優秀な人材を獲得するなら、応募者一人ひとりに敬意をもって迅速かつ丁寧に対応し、「この会社で働きたい」と思ってもらえるように心がけましょう。
7.面接ではアイスブレイクを大事にする
アイスブレイクとは、初対面の人同士が、本題に入る前に緊張をほぐすためのコミュニケーションの手法です。面接の際にアイスブレイクを意識することで、応募者が自己アピールしやすくなり、自社に合っているかどうかを判断しやすくなります。最初は、天気や会場までの道のりといった簡単な話題で場を和ませることで、応募者をリラックスさせましょう。また、むやみに否定的な言動をするのではなく、応募者の考えに共感を示すことで話しやすい雰囲気を作りましょう。
8.自社の良い面ばかりをアピールしない
求職者に対し、企業の魅力だけでなく、抱えている課題や仕事の厳しい側面も正直に伝えることが重要です。ネガティブな面を正直に伝えることで、入社後の期待値のズレによるミスマッチを防ぎ、早期離職の可能性を抑えられます。課題をオープンに話す企業姿勢は、求職者からの信頼獲得につながり、入社後も長期的に良好な関係を築きやすくなります。面接で良い面と悪い面をしっかり伝えるほか、求職者からの質問に正直に答えることも意識しましょう。
9.採用対象者の幅を広げられないか検討する
正社員を募集してもなかなか集まらない場合は、簡単な仕事を任せられる、アルバイトや契約社員などの募集ができないか検討してみましょう。また、外国人や障がい者の雇用に力を入れることでも、採用対象者の幅を広げられます。外国人や障がい者の雇い入れについては、助成金を支給してもらえる可能性もあるため、採用コストの低減も期待できます。ただし、これまでと異なるバックグラウンドの人を採用する際は、どういったリスクがあるかも考え、社内で慎重に準備を進めるとよいでしょう。
10.人材採用に関する助成金を活用する
特定の要件を満たして人材を採用すると、国や地方自治体から助成金を受給できるケースがあります。たとえば、高年齢者や障がい者などの就職困難者を受け入れる「特定求職者雇用開発助成金」や、正規雇用を前提に求職者を試行雇用する「トライアル雇用助成金」など。採用コストが気になってなかなか採用活動に踏み切れないときは、助成金を利用できないか検討するのも一つの手です。厚生労働省や管轄のハローワークのウェブサイトで助成金の最新情報を確認し、活用できるものがないか調べてみましょう。
まとめ:採用時のポイントを把握して、優秀な人材を確保しよう
本記事では、労働人口の減少や採用コストの上昇など、人材採用を難しくする要因について解説し、それを乗り越えるための人材採用を成功に導く10のポイントや、代表的な採用手法などを解説しました。
人材採用難の時代を乗り切るためには、様々な手法を駆使し採用コストを抑えつつ、より多くの求職者にアプローチできる採用活動が不可欠です。また、採用後のミスマッチを防ぐためにも、企業の事業内容や社風を正確に、誇張なく伝えることを意識して採用活動を行いましょう。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。