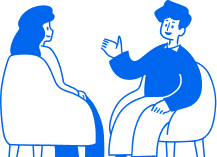「応募数を増やすにはこのやり方であっているのか?」「どうして採用が進まないのかわからない」
経験や勘に頼った採用活動は、時間とコストを浪費し疲弊を招きかねません。
特に採用人数が多い場合や、特定職種がなかなか決まらない場合、漠然とした不安を抱えたままでは、戦略的な次の一手を打つのは難しいでしょう。
この記事では、採用活動を数値で「見える化」し、課題解決に導くための強力なツール「採用KPI」について徹底解説します。
| ステップ |
歩留まり率 (目安) |
算出式 | 目標人数 |
| KGI:内定承諾 | - | - | 3名 |
| 内定 | 50%(内定承諾率) |
内定承諾目標人数÷内定承諾率 3名÷50%=6名 |
6名 |
| 最終面接 | 50%(最終面接通過率) | 内定者÷最終面接通過率 6名÷50%=12名 |
12名 |
| 一次面接 | 30%(一次面接通過率) |
最終面接者÷一次面接通過率 12名÷30%=40名 |
40名 |
| 書類選考 | 30%(書類選考通過率) | 一次面接者÷書類選考通過率 40名÷30%=134 |
134名 |
| KPI:応募者 | 134名 |
採用KPIを活用すると、上記のように、目標採用人数(KGI)が3名の場合、応募者(KPI)は134名必要になる、といった具体的な数値に基づいた戦略を練ることができるようになります。
採用KPIの定義から、すぐに使える具体的な設定方法、そして成果につなげるための活用ポイントまで、分かりやすくお伝えします。
客観的なデータに基づいた戦略的な採用活動へと踏み出す一歩に、是非お役立てください。
目次
そもそも採用KPIとは?感覚的な採用から脱却するための指標
採用KPI(ケーピーアイ)は、採用活動を客観的に評価し、成功に導くための「ものさし」です。
KPIとは「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」の略称であり、目標達成に向けたプロセスが適切に進んでいるかを定量的に把握するための指標を指します。
採用活動におけるKPIは、単に「応募が多かった」「面接で良い人がいた」といった感覚や経験ではなく、データに基づいて採用活動の状況を把握し、改善を進めるためのツールです。
これにより、属人的で感覚的な採用から脱却し、再現性のある戦略的な採用活動を実現することができます。
KGIとの違いは「最終目標」か「中間目標」か
KPIを理解する上で、KGI(ケージーアイ)との違いを明確に理解しておく必要があります。
結論から言えば、KPIは「中間目標」であり、KGIは「最終目標」です。
KGIは「Key Goal Indicator(重要目標達成指標)」の略称で、最終的に達成すべきビジネスにおけるゴールを指します。
採用活動におけるKGIは、多くの場合「いつまでに、どの職種を、何名採用するか」という具体的な採用目標になります。
【KGIとKPIの関係性(例)】
KGI(最終目標):「今年度中にエンジニアを5名採用する」
KPI(中間目標):KGIを達成するために必要な「応募者数」「書類選考通過率」「最終面接の実施数」「内定承諾率」など
最終目標であるKGIを達成するために、採用プロセスの中の各段階で追うべき中間目標がKPIである、とシンプルに捉えましょう。
なぜ採用活動にKPIの設定が必要なのか?3つのメリット
採用KPIを設定し、計測するのには手間がかかりますが、それを上回る大きなメリットがあります。ここでは、採用活動にKPIの設定が必要な3つの理由を紹介します。
- 課題の可視化と改善点の特定ができる
- 関係者への客観的な説明と合意形成がしやすくなる
- データに基づいた効率的な採用活動が実現する
この3点の理由について解説します。
1.課題の可視化と改善点の特定ができる
KPIを設定する最大のメリットは、採用プロセスの課題を可視化し、改善点をピンポイントで特定できることです。
「応募は来るが、なぜか内定承諾に至らない」といった漠然とした悩みも、KPIを設定すれば「応募」から「承諾」までのプロセスのどこに問題があるかを数値で特定できます。
例えば、「一次面接の通過率」というKPIが極端に低い場合、以下のような仮説が立てられ、的確なアクションに繋げられます。
仮説:面接官の評価基準がバラバラになっている、または面接官のスキルに差があるのではないか。
具体的な改善策:面接官トレーニングを実施する、評価シートの見直しを行う。
感覚ではなく、データに基づいて的確なアクションを起こせるようになることが、KPI活用の最大の利点です。
2.関係者への客観的な説明と合意形成がしやすくなる
採用KPIは、経営層や現場の責任者など、採用に関わるすべての人にとっての「共通言語」になります。以下に例をあげて解説します。
【KPIがない場合の報告】
「応募は頑張って集めていますが、最近は内定辞退が多くて困っています…」
(曖昧で、課題の原因も解決策も不明確)
【KPIがある場合の報告】
「今月は目標応募者数80名に対し、75名と若干未達です。また、内定承諾率が先月の60%から40%に低下しており、内定者フォローの強化が必要です」
(課題が明確で、具体的なアクションと予算の必要性が伝わる)
このように客観的なデータを用いることで、経営層への報告の説得力が高まり、採用予算の獲得や、現場責任者への面接協力依頼などもスムーズに進むようになります。
3.データに基づいた効率的な採用活動が実現する
限られた採用リソース(時間、予算、人員)を最大限に活かすためには、効率的な活動が不可欠です。KPIは、費用対効果を明確化し、採用活動全体の生産性を高めます。
例えば、「求人媒体ごとの応募者数」や「内定承諾率」を計測することで、以下のような戦略的な判断が可能になります。
- 応募単価の高い媒体でも、内定承諾率が高ければ継続投資する。
- 応募は多いが、書類選考の歩留まりが悪い媒体からは、ターゲット層が集まっていないと判断し、掲載を停止・見直す。
データに基づいて「やるべきこと」と「やめるべきこと」を判断できるようになるため、採用活動のムダをなくし、効率的な目標達成が可能になります。
【4ステップ】明日から使える採用KPIの具体的な設定方法
採用KPIは、難しく考える必要はありません。採用の最終目標(KGI)から逆算すれば、誰でも簡単に、かつ具体的に目標数値を設定できます。
ここでは、明日から使える採用KPIの具体的な設定手順を4つのステップで解説します。
- ステップ1.採用の最終目標(KGI)を決める
- ステップ2.採用プロセスを分解し、各段階を洗い出す
- ステップ3.各段階の歩留まり率を算出し、ボトルネックを探す
- ステップ4.KGIから逆算して各プロセスのKPI(目標数値)を設定する
ステップ1.採用の最終目標(KGI)を決める
まず、最終的なゴールであるKGIを明確に定義します。KGIが曖昧だと、KPIもブレてしまうため、このステップが最も重要です。
「いつまでに」「どの職種を」「何名採用するか」を具体的に定義しましょう。
良い例
2024年3月末までに、営業職(正社員)を3名採用する。
悪い例
良い人がいれば、今年は採用したい。
良い例のように、期限、職種、人数を具体的に設定することで、逆算のための基準ができます。
ステップ2.採用プロセスを分解し、各段階を洗い出す
次に、自社の採用プロセスを分解し、応募から入社までの道のりを洗い出します。これにより、採用活動の全体像を把握し、どこにKPIを設定すべきかを見極めます。
一般的な採用プロセスは以下の6段階で洗い出すことができます。
- 応募(母集団形成)
- 書類選考
- 一次面接
- 最終面接
- 内定
- 内定承諾
ステップ3.各段階の歩留まり率を算出し、ボトルネックを探す
洗い出した各選考段階について、過去の実績データから「歩留まり率」を確認します。
歩留まり率とは、一つ前の段階に進んだ人数に対する、次の段階に進んだ人数の割合です。
以下の計算式で出すことができます。
歩留まり率(%)=(次の段階に進んだ人数÷その段階にいた人数)×100
過去データがない場合の目安については以下のとおりです。
- 書類選考通過率:30%
- 一次面接通過率:30%
- 最終面接通過率:50%
この歩留まり率を計算することで、採用プロセスの中でどこが最も人を絞り込んでいるか、つまりボトルネックが見えてきます。
ステップ4.KGIから逆算して各プロセスのKPI(目標数値)を設定する
最後に、ステップ1で決めたKGIをゴールとして、ステップ3で確認した歩留まり率を使って、必要な応募者数を逆算していきます。
| ステップ |
歩留まり率 (目安) |
算出式 | 目標人数 |
| KGI:内定承諾 | - | - | 3名 |
| 内定 | 50%(内定承諾率) |
内定承諾目標人数÷内定承諾率 3名÷50%=6名 |
6名 |
| 最終面接 | 50%(最終面接通過率) | 内定者÷最終面接通過率 6名÷50%=12名 |
12名 |
| 一次面接 | 30%(一次面接通過率) |
最終面接者÷一次面接通過率 12名÷30%=40名 |
40名 |
| 書類選考 | 30%(書類選考通過率) | 一次面接者÷書類選考通過率 40名÷30%=134 |
134名 |
| KPI:応募者 | 134名 |
この逆算により、「営業職3名採用」のKGIを達成するには、約134名の応募者というKPIが設定できます。
これにより、ゴール達成のために「何を」「どれだけ」すべきかが明確になり、採用活動の最初の段階(応募者数の確保)から戦略を立てられるようになります。
これだけは押さえたい!採用活動で使われる主要なKPI一覧
採用KPIには非常に多くの種類がありますが、最初からすべてを追う必要はありません。まずは以下の主要なKPIの中から、自社の課題に合った2~3個を選んで計測を始めることをお勧めします。
ここでは、主要なKPIを「量」「質・効率」「コスト」「採用後」の4つのカテゴリに分けて紹介します。
-
量に関するKPI(応募数・母集団形成)
-
質・効率に関するKPI(通過率・歩留まり率)
-
コストに関するKPI(採用単価)
-
採用後に関するKPI(定着率)
1.量に関するKPI(応募数・母集団形成)
採用活動の入り口、つまり応募者の「数」を測る指標です。母集団形成が課題となっている場合に特に重要になります。
| KPI | 概要 |
| 応募者数 | 一定期間に集まった応募者の総数。採用計画達成の土台となる最も重要な指標。 |
| 媒体別応募数 | 求人媒体や採用チャネル(自社HP、SNSなど)ごとの応募者数。媒体の有効性を測るのに役立つ。 |
| スカウト承諾率 | 送信したスカウトメールに対し、応募(面談)を承諾した人の割合。スカウト文面やターゲティングの適切さを測る。 |
2.質・効率に関するKPI(通過率・歩留まり率)
選考プロセスの効率性や、採用の質を測る指標です。前述の通り、プロセスのボトルネック発見に役立ちます。
| KPI | 概要 |
| 書類選考通過率 | 応募者総数に対する、書類選考を通過した人数の割合。 |
| 面接通過率 | 各面接(一次、最終など)の実施人数に対する、次の段階に進んだ人数の割合。 |
| 内定承諾率 | 内定を出した人数に対する、内定を承諾し入社を決めた人数の割合。特にこの率が低い場合は、選考中の企業魅力付けや内定者フォローに課題がある可能性を指摘できる。 |
3.コストに関するKPI(採用単価)
採用活動に投じた費用対効果を測る指標です。費用面での効率性を評価できるため、経営層への報告にも非常に重要となります。
| KPI | 概要 |
| 採用単価(CostperHire) |
1人あたりにかかった採用コスト。 採用コスト総額(媒体費、人件費、紹介料など)÷採用人数 |
4.採用後に関するKPI(定着率)
採用は入社して終わりではなく、組織に定着してこそ成功と言えます。採用のミスマッチを測る指標です。
| KPI | 概要 |
| 入社後定着率 | 一定期間後に在籍している社員の割合。採用の質とミスマッチの少なさを示す。 |
| 面接通過率 | 各面接(一次、最終など)の実施人数に対する、次の段階に進んだ人数の割合。 |
採用KPIを設定した後にやるべきこと|成果につなげる運用ポイント
KPIは設定することがゴールではありません。
設定した後の「運用」が最も重要です。KPIを単なる数字で終わらせず、成果につなげるための2つの運用ポイントを紹介します。
1.数値を定期的に計測し、チームで共有する
設定したKPIは、必ず定期的に(週1回または月1回など)計測し、数値を可視化しましょう。
さらに重要なのは、その数値を採用担当者だけでなく、面接官や現場責任者など関係者全員で共有することです。
数値をグラフなどで「見える化」して共有することで、チーム全体の「今、何が起きているか」という現状認識が統一され、目標達成に対する意識とモチベーションが高まる効果があります。
2.PDCAサイクルを回し、継続的に改善する
KPIが目標数値に達しなかったとしても、それは決して失敗ではありません。
改善のチャンスと捉え、PDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)を回し続けましょう。
P(Plan/計画):KGIとKPIを設定する
D(Do実行):設定に基づき採用活動を実施する
C(Check/評価・分析):KPIの計測結果を分析し、目標との乖離を確認する
A(Action/改善):乖離の原因を特定し、改善策を立案・実行する
【例:PDCAの流れ】「書類選考通過率が目標の30%に対し、20%だった」
C(評価・分析):なぜ20%になったのか?
→原因分析(求めるスキル要件が求人票に明確に書かれていなかった、など)
A(改善):書類選考の基準を見直し、求人票の記載内容をより具体的に修正する。
このサイクルを地道に回すことが、採用力強化の最も確実な方法です。
【要注意】採用KPI導入でよくある失敗と対策
採用KPIは強力なツールですが、使い方を間違えると混乱を招く可能性があります。
ここではよくある失敗例と対策をお伝えします。採用KPIによるスムーズな運用の参考にしてみてください。
失敗例1.設定したKPIが多すぎて管理しきれない
KPIを設定しすぎて、計測と管理だけで手一杯になり、肝心の「改善アクション」に手が回らなくなるケースです。指標が多すぎると、どの数値が重要なのかも分からなくなり、KPIが形骸化してしまいます。
【対策】最初は指標を3つ程度に絞る
まずは「量」「質」「コスト」のカテゴリから、それぞれ1つずつ(例:応募者数、内定承諾率、採用単価)といった具合に、最も重要な指標に絞って計測を始めることがおすすめです。運用に慣れてきたら、少しずつ指標を増やしていきましょう。
失敗例2.数値を追うこと自体が目的になってしまう
KPIの達成が目的化し、本来のゴールであるKGIを見失うという本末転倒な失敗です。
例えば、「応募者数」というKPIだけを追い求めた結果、募集のハードルを下げすぎてターゲット外の応募ばかりが増え、選考工数が増大し、かえって採用の質が低下する例などがあります。
【対策】常にKGIとセットでKPIを見る
KPIはKGI達成のための「中間目標」であることを常に意識し、KPIの達成がKGIの達成に貢献しているかをチェックし続けましょう。
特に「量」のKPIを追う際は、必ず「質」のKPI(例:面接通過率、内定承諾率)も併せて見ることで、バランスの取れた活動を維持できます。
まとめ:採用KPIで戦略的な採用へ。
本記事で解説した採用KPIは、客観的なデータに基づき採用活動を成功に導くための強力なツールです。
KGI(最終目標)とKPI(中間目標)を明確にし、採用プロセスを分解して歩留まり率を算出することで、ボトルネックを特定し、KGIから逆算してKPIを設定します。
主要なKPIには「量」「質・効率」「コスト」「採用後」に関するものがあります。
KPIは設定後、定期的に計測しチームで共有し、PDCAサイクルを回して継続的に改善することが重要です。
KPIが多すぎたり、数値を追うことが目的になったりする失敗を避け、KGIとセットでKPIを見ながら運用することで、データに基づいた戦略的な採用活動を実現させましょう。
北海道での採用なら、アルバイトも正社員もHAJにお任せください
KPIを設定し、その効果を分析するためには、まず適切な母集団(応募者)を集めることが不可欠であり、どの採用媒体を選ぶかはKPI戦略の最初の重要なステップとなります。
北海道内での採用に課題をお持ちでしたら、北海道の採用市場を熟知したプロフェッショナルである北海道アルバイト情報社(HAJ)にご相談ください。
- アルバイト・パート採用には:札幌・市内近郊で50年以上の歴史がある「アルキタ」、道内全域で地域に密着した「シゴトガイド」、主婦に特化した「しゅふきた」
- 正社員・契約社員の採用には:道内全域で多様な職種に対応する「ジョブキタ」
を提案いたします。
単なる媒体掲載だけでなく、本記事で解説したような採用KPIの設定に関するご相談や、採用計画全体のサポートまで、御社の課題に寄り添った採用活動も支援いたします。お気軽にお問い合わせください。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。