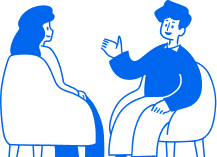「不採用の理由を教えてください」
採用活動において、応募者からこのように質問された経験がある採用担当者は少なくないでしょう。しかし、安易に答えてしまえば、トラブルに発展するリスクもゼロではなく、この質問にどう答えるのが正解なのか、悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
この記事では、不採用の理由を聞かれた際の適切な対応方法と、その際に知っておくべきリスクについて詳しく解説します。
なぜ求職者は不採用理由を聞きたいのか
応募者が不採用理由を聞く背景には、いくつかの心理が隠されています。
- 自己成長のため:自身の何が足りなかったのかを知り、今後のキャリアアップに活かしたい。
- 納得したい:手応えがあった面接だったのに不採用になった。その理由を知ることで、選考結果に納得したい。
- 企業への不信感:不誠実な対応や、納得できない選考結果に不信感を抱き、理由を追及したい。
これらの背景を理解し、できる範囲で誠実に対応することが、企業のブランドイメージを保つ上でも重要です。しかし、誠実さとリスクヘッジのバランスを慎重に考える必要があります。
具体的な対応方法とポイント
ここからは不採用理由を聞かれたらどうするのが正しいか解説します。
原則として、企業側に不採用理由を伝える義務はありません。日本の多くの企業では、不採用理由を開示しないのが一般的な対応となっています。これは、後述する法的なリスクやトラブルを避けるためです。
しかし、テンプレート通りの返信で済ませるだけでは、企業のイメージを損なう可能性もはらんでいます。特に、最近ではSNSの普及により、不適切な対応が拡散され、企業の評判に悪影響を及ぼすケースも散見されます。
では、具体的な対応方法について、以下2つのアプローチについて解説します。
- 理由を明かさない場合
- 差し支えない範囲で伝える場合
1.理由を明かさない場合
多くの企業が採用しているアプローチです。以下のような表現を用いて、丁寧に回答を拒否するのが一般的です。
「選考結果は総合的な判断に基づくものであり、個別の理由についてはお答えしかねます。」
「今回は誠に残念ながら、貴意に沿うことができませんでした。ご期待に沿えず大変申し訳ございませんが、何卒ご容赦ください。」
この返答をテンプレートとして用意しておき、どの応募者に対しても同じ回答をすることで、公平性を保ちつつトラブルを避けることができます。ポイントは、「総合的な判断」といった抽象的な表現を使うことです。
2.差し支えない範囲で伝える場合
ごく稀なケースですが、差し支えない範囲で理由を伝えることも可能です。ただし、その際は細心の注意を払う必要があります。
例えば、スキル不足や経験不足など、客観的な事実に基づいた理由であれば、伝えることができる場合もあります。
「今回は、特定のプログラミング言語の経験が必須となるポジションでした。〇〇様のスキルセットも大変魅力的でしたが、今回のポジションの要件を満たすには、その特定の言語経験が不足していると判断いたしました。」
この際、応募者の人格やパーソナリティを否定するような表現は絶対に避けてください。 「協調性がない」「熱意が感じられない」といった主観的な表現は、応募者の感情を逆なでし、トラブルの原因となり得ます。
あくまで、客観的事実に基づいた、特定のポジションにおける要件とのミスマッチとして伝えることが重要です。
不採用理由を伝えることのリスク
不採用理由を安易に伝えることには、以下の3つのリスクが伴います。
- 応募者とのトラブル・訴訟のリスク
- 採用基準の固定化、形骸化
- 応募者との無用なやり取りの増加
この3点のリスクについて解説します。
1.応募者とのトラブル・訴訟のリスク
不採用理由を聞いた応募者が、その内容に納得せず、企業に対して異議を唱えたり、時には訴訟を起こしたりする可能性もゼロではありません。
- ハラスメント:不採用理由がセクハラやパワハラと受け取られる可能性。
- 差別:性別、年齢、国籍、思想・信条などを理由にした不採用と解釈される可能性。
これらのリスクを避けるためにも、多くの企業は不採用理由を開示しない方針をとっています。
2.採用基準の固定化、形骸化
不採用理由を伝えることを前提に選考を進めてしまうと、「不採用理由を説明しやすい」という視点で応募者を判断してしまう可能性があります。これは、本来評価すべき応募者のポテンシャルや多様なスキルを見落とすことにつながり、採用基準が固定化・形骸化してしまうリスクがあります。
3.応募者との無用なやり取りの増加
不採用理由を開示すると、応募者からさらに詳細な説明を求められたり、「なぜ?」という質問が繰り返されたりする可能性が高まります。採用担当者の業務は多忙であり、個別のやり取りに時間を割くことは現実的ではありません。
まとめ:リスクを最小限に抑えつつ、企業のブランドイメージを守るための適切な対応を
不採用の理由を聞かれた際は、以下のポイントを押さえて対応しましょう。
- 個別の開示義務はないことを理解する。
- 基本的にはテンプレート通りの回答で丁寧にお断りする。
- どうしても伝える場合は、客観的事実に基づいて、ポジションとのミスマッチを伝える。
- 応募者の人格やパーソナリティを否定する表現は絶対に避ける。
不採用通知は、応募者にとっては非常に残念なものです。たとえ不採用であったとしても、選考を受けてくれたことへの感謝を伝え、丁寧に対応することで、企業の誠実さをアピールできます。
採用担当者として、リスクを最小限に抑えつつ、企業のブランドイメージを守るための適切な対応を心がけましょう。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。