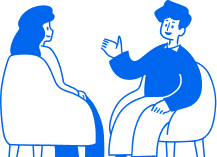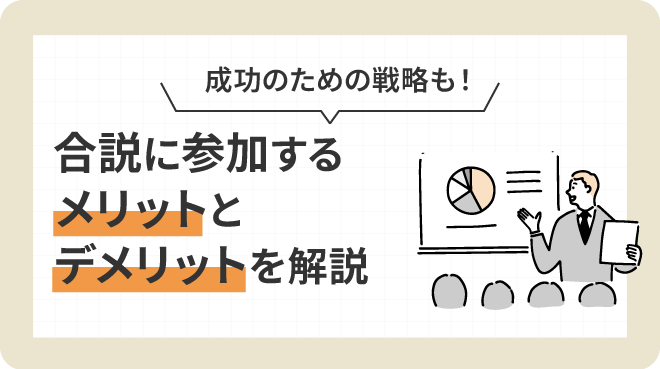
採用活動において、合同企業説明会(以下、合説)は多くの企業が取り入れる採用手段の一つです。しかし、ただ参加するだけでは期待した効果を得ることは難しいでしょう。
この記事では、北海道の人事担当者が合説を最大限に活用するために知っておくべき、参加するメリットとデメリット、そして成功のための具体的な戦略について詳しく解説します。
合説に参加する4つのメリット
企業が合説に参加する主なメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 求職者との直接接触機会の創出
- 自社の魅力を五感を通じて効率的に伝えられる
- 採用活動におけるコスト効率の向上
- 競合他社との直接比較による差別化のチャンス
それではこの4つのメリットについて解説していきます。
1.求職者との直接接触機会の創出
合説の最大のメリットは、一度に多くの求職者と直接対話できる点です。自社単独の説明会では、集客のために多大な広告費用や人的リソースが必要となり、リーチ数に限界があります。一方、合説は主催者が広く告知を行うため、企業の認知度が低い中小企業やベンチャー企業であっても、普段接点のない多様な求職者と出会う貴重な場となります。
2.自社の魅力を五感を通じて効率的に伝えられる
求人票だけでは伝わりにくい社内の雰囲気や社員の人柄を、実際にブースで対話することで伝えることができます。求職者は「この会社で働く人はどんな人だろう?」という興味を強く持っています。
人事担当者だけでなく、現場の若手社員や中堅社員が参加し、直接対話できれば、リアルな働き方や職場の雰囲気を具体的にイメージしてもらうことが可能です。これにより、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
また、ブース内でのデモンストレーションや事例紹介によって、自社ならではの技術やソリューションを効果的にアピールすることもできます。また、一方的に企業情報を伝えるのではなく、対話形式を意識してみると良いでしょう。
3.採用活動におけるコスト効率の向上
合説への参加には、参加費用やブース設営費がかかりますが、個別の説明会を複数回開催する手間やコストと比較すると、効率的な採用活動が実現できます。
また、自社説明会の開催場所を確保したり、イベントの企画・運営に割く手間が省けるため、人事担当者の業務負担軽減にも繋がります。
4.競合他社との直接比較による差別化のチャンス
合説は、多くの競合他社と隣接してブースを構えるため、求職者から直接的な比較検討の対象となります。これは一見デメリットにも思えますが、自社の独自性や強みを際立たせる絶好の機会でもあります。
他社にはないユニークな企業文化、福利厚生、キャリアパスなどを伝えることで、求職者の印象に深く残り、選考への関心を高めることができます。この直接比較の場で、自社のポジションを再確認し、採用戦略を磨くためのヒントを得ることも可能です。
合説に参加する4つのデメリット
合説には参加するメリットもありますが、うまく活用できないとデメリットもでてきます。ここでは以下の4つのデメリットについて解説します。
- 多くの情報の中に埋もれてしまうリスク
- 採用ターゲットとのミスマッチ
- 費用対効果の不透明さ
- 他社との差別化に苦戦する可能性
1.多くの情報の中に埋もれてしまうリスク
合説は多くの企業が集まるため、求職者の関心が分散しやすく、自社ブースに人が集まらないリスクがあります。特に知名度の高い大企業や人気企業と同じ会場に出展する場合、自社の魅力が埋もれてしまう可能性も否定できません。多くのブースの中から目を引くためには、ブースの装飾やデザインを工夫したり、積極的にブースに訪れた方に声かけを行うなど、他社との差別化を図るための戦略が不可欠です。
2.採用ターゲットとのミスマッチ
合説の来場者は、様々な業界・職種に興味を持つ層であり、まだキャリアの方向性が定まっていない方も少なくありません。そのため、自社が求める特定のスキルや志向性を持った求職者に効率的に出会うことは難しい場合があります。
広くアピールする一方で、本当に自社にマッチする人材を見極めるための質問や対話のスキルが求められます。ブースでの対話を通じて、その人が自社の文化や仕事内容にどれだけフィットするかを見抜く眼力を養う必要があります。
3.費用対効果の不透明さ
合説への参加費用は決して安くありません。そして、参加したからといって、必ずしも期待した数の求職者が選考に進んでくれるとは限らず、何人の内定者が出るかという費用対効果は、事前にはわかりません。
単に求職者を集めるだけでなく、その後の選考プロセスへの誘導や、入社意欲を高めるためのフォローアップ体制を整えるなど、合説参加後の戦略まで含めて効果を測定・分析することが重要です。
4.他社との差別化に苦戦する可能性
合説では多くの企業が似たような説明を行い、同じような採用メッセージを発信しがちです。そのため、自社の独自性を打ち出すのが難しくなることがあります。単に事業内容や給与・福利厚生を説明するだけでなく、なぜこの会社で働くのか、どんなやりがいがあるのかといった「ストーリー」を語る力が求められます。心に響くような、共感を呼ぶメッセージを発信できなければ、他社の中に埋没してしまうでしょう。
合説を成功させるための実践的戦略とフロー
合説に参加するときには、ただなんとなく参加しても望ましい結果は得られません。合説に参加し成功させるためには、実践的な戦略が必要です。ここでは以下3つのフローについて解説します。
- 事前準備:成功の鍵は周到な計画
- 当日の対応:求職者との対話を深める
- 参加後のフォロー:熱意を冷まさない工夫
1.事前準備:成功の鍵は周到な計画
合説の成功の第一歩は事前準備が必要不可欠です。何度も合説に参加していると慣れてきておざなりにしてしまいがちですが、しっかり確認し、もし複数人で参加する場合は事前に認識を共有しておくことも大切なポイントです。
- ターゲットの明確化: どのような求職者にブースに来てほしいのか、具体的な人物像を定めます。
- ブース設計の工夫: 遠くからでも目を引くブースデザイン、キャッチーな看板やポスター、求職者が立ち寄りやすい雰囲気作りを意識します。
- プレゼンテーション内容の精査: 簡潔で分かりやすい会社紹介、求職者に「聞きたい」と思うようなテーマ(実際の仕事内容、キャリアパスなど)を盛り込みます。
- SNSを活用した事前告知: 開催日や場所を事前にSNSで告知し、自社に興味を持った方に来場を促します。
2.当日の対応:求職者との対話を深める
入念な準備をしたうえで、実際に求職者と話す当日にも気をつけたいポイントがあります。
- 役割分担の徹底: 誰が会社説明を行い、誰が質問に答えるかなど、役割を明確にします。人事担当者だけでなく、若手社員や募集部門の担当を参加させるときには、どんな話を誰が担当するかを分担しておきましょう。
- ブース来場者への積極的な声かけ: 「どのような業界に興味がありますか?」といった軽い質問から入り、対話のきっかけを作ります。もし着席を悩んでいるようであれば、自社のことを一方的に話すのではなく、相手がどんな情報を求めているか探りながら対話していくのもポイントです。
- 個別対応の強化: 一人ひとりに時間をかけ、質問に丁寧に答えることで、信頼関係を築きます。
3.参加後のフォロー:熱意を冷まさない工夫
合説に参加した来場者には積極的に接触を試みます。自社主催の単独説明会や見学への誘導、応募への促しなど、次のアクションを起こしてもらうためには、以下のポイントに気をつけて対応していきましょう。
- 迅速な連絡: 合説で話した求職者には、できるだけ早く感謝のメールを送り、個別の説明会や選考への参加を促します。可能であれば、全員一律のテンプレメールではなく、その方と話した内容で覚えている個別の話題を一言添えると好印象です。ただし、記憶違いには十分気をつけましょう。
- 専用の窓口の設置: 合説参加者専用の質問フォームや連絡先を用意することで、求職者が気軽に相談できる環境を整えます。もしそこに連絡が入った場合も迅速に対応することが求められます。
- データ分析: どの合同企業説明会に何人の求職者が訪れたか、その後の選考参加率や内定率などをデータで分析し、次回の改善に生かします。
まとめ:事前準備から当日の対応、参加後のフォローまで一貫を!
合同企業説明会は、人事担当者にとって多くの求職者と出会い、自社の魅力を直接伝えられる有効な採用手法です。しかし、単にブースを出すだけでは、その効果は限定的です。デメリットを理解し、それを克服するための明確な戦略を立て、事前準備から当日の対応、参加後のフォローまでを一貫して行うことが、合説での成功の鍵となります。合説を戦略的な採用活動の一環として位置づけ、効果的な人材獲得を実現しましょう。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。