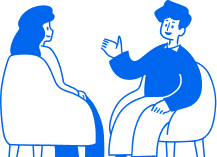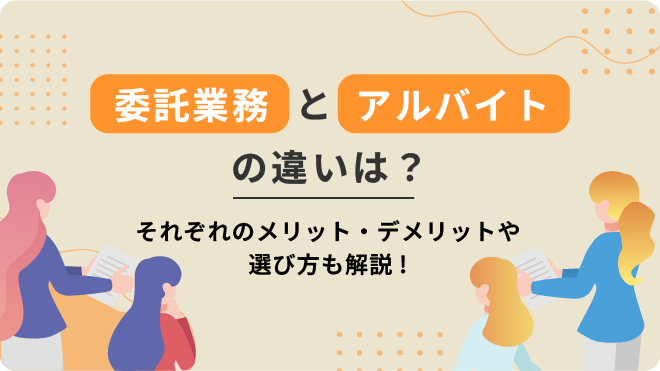
近年、働き方の多様化により、企業が出す求人には正社員やアルバイト以外に業務委託という選択肢も増えています。しかし、採用担当者のなかには「業務委託とアルバイトはどう違うの?」「どちらを採用すべき?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
本記事では、業務委託とアルバイトの違いを明確にし、それぞれのメリット・デメリットや選び方のポイントを詳しく解説します。どちらの採用を検討すべきか悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考に、自社のニーズに合った最適な人材確保の方法を見つけてください。
目次
業務委託とアルバイトの違い
業務委託とアルバイトの違いを具体的に見ていきましょう。確認するのは以下の4つのポイントです。
契約内容
報酬の支払い方法
福利厚生
年末調整の有無
それぞれの違いを理解することで、自社のニーズに合った採用方法を判断しやすくなります。採用活動を始める前に、ぜひ確認してみてください。
●契約の内容
業務委託とアルバイトでは、企業との契約内容が根本的に異なります。
業務委託は、企業と業務委託契約を結びます。企業との関係は対等で、特定の業務や成果物の完成に対して報酬を支払われるのが特徴です。また、企業からの指揮命令は受けず、自分の裁量で仕事を進めることができます。
一方、アルバイトは、企業と雇用契約を結び、労働力を提供することで賃金を受け取ります。企業と労働者の間には指揮命令関係が発生するため、労働時間や業務内容など、企業の定めたルールに従って働く必要があります。
業務委託契約の種類
業務委託契約は、その内容によってさらに以下の3つに分類されます。
-
請負契約:依頼された「仕事の完成」に対して報酬が支払われる契約です。
-
委任契約:法律行為の事務処理を依頼する契約です。
-
準委任契約:法律行為以外の事務処理を依頼する契約です。
いずれの契約も、業界のプロフェッショナルに仕事を依頼する点で共通しています。どの契約形態を選ぶかは、仕事の内容や職種によって異なりますが、いずれの場合も業務委託契約の特性を理解した上で進めることが重要です。
●報酬(対価)の支払い方法
仕事に対して支払われる報酬(対価)は、業務委託とアルバイトで異なります。業務委託の報酬は、労働時間ではなく、提供するスキルや成果物の価値に応じて決まります。そのため、効率よく作業し、質の高い成果物を納品することが収入アップにつながります。支払いタイミングは契約により、成果物の納品時や業務完了時などさまざまです。一方、アルバイトの報酬は時給や日給など、働いた時間や日数によって決まり、雇用契約で決められた時間を超えて働いた場合は残業代も支払われます。このように、報酬の決め方が両者で大きく異なるのが特徴です。
●福利厚生
業務委託で働く場合、企業と雇用関係を結ばないため、社会保険や雇用保険、労災保険といった法定福利厚生は適用されません。そのため、国民健康保険や国民年金に自分で加入し、保険料も全額自己負担となります。また、通勤手当や住宅手当といった企業独自の福利厚生も原則として適用されません。 一方、アルバイトは一定の条件を満たせば社会保険に加入でき、保険料の一部を会社が負担してくれるため、自己負担を抑えつつ病気やケガなどに備えることができます。福利厚生の面では、業務委託よりアルバイトのほうが手厚いと言えるでしょう。
●年末調整の有無
年末調整は、給与から源泉徴収された所得税額と、本来納めるべき税額との差額を調整する手続きです。企業に勤めるアルバイトの場合、原則として会社が年末調整を行います。ただし、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合や年収が一定額を超える場合は、自分で確定申告が必要です。一方、業務委託は雇用関係にないため、企業が年末調整を行うことはありません。したがって、報酬から源泉徴収されている場合でも、業務委託で働く人は自身で確定申告をして所得税額を精算する必要があります。企業は、アルバイトを採用する際に年末調整の手間を考慮する必要があります。
業務委託を採用するメリット・デメリット
業務委託を採用するメリット・デメリットには、以下のようなものが挙げられます。
| メリット | デメリット |
|
専門性の高い人材を確保できる |
コミュニケーションコストが高い |
|
人件費を抑えやすい |
情報漏えいのリスクが増える |
|
社内リソースを空けられる |
ノウハウが社内に残りにくい |
業務委託の最大のメリットは、高い専門性を持つ人材を教育なしで活用でき、必要な時だけ単発・短期間で仕事を依頼できるため、コストを抑えやすい点です。 この柔軟性は、特定のプロジェクトや一時的な人手不足に対応する上で非常に有効です。
一方で、デメリットとして挙げられるのは、社内に常駐しないことによるコミュニケーションコストの増加です。また、外部の人間と機密情報を共有することになるため、情報漏えいのリスクも考慮しなければなりません。これらのリスクを管理するためには、明確な契約や厳格なセキュリティ対策が不可欠です。業務委託の活用は、これらのメリットとデメリットを理解した上で慎重に判断することが重要です。
アルバイトを採用するメリット・デメリット
アルバイト採用には、コミュニケーションの取りやすさや人材育成のノウハウ蓄積といったメリットがある一方で、人件費増や管理工数の増加といったデメリットも存在します。
|
メリット |
デメリット |
|
コミュニケーションが円滑 |
人件費が増えやすい |
|
人材育成のノウハウ蓄積 |
専門人材の確保が困難 |
|
人員補充が容易 |
管理コストが発生 |
アルバイトを採用する最大の利点は、社内でのコミュニケーションが取りやすく、業務の進捗管理や指示がしやすい点です。 これにより、OJT(On-the-Job Training)を通じて人材育成のノウハウを社内に蓄積できます。さらに、人員の補充も比較的容易に行えます。
しかし、デメリットとして、業務委託と異なり、残業代の支払いなどが発生するため、長期契約では人件費が増加しやすい点が挙げられます。また、特定の専門知識を持つ人材の確保が難しく、教育に時間やコストがかかる場合もあります。これらの特性を理解した上で、業務内容や目的に応じて最適な雇用形態を選ぶことが重要です。
有給休暇について
アルバイトの長期契約の場合には、人件費が増加しやすい要因の一つとして有給休暇の付与があります。有給休暇は正規・非正規を問わず、「6カ月間の継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の条件を満たせば付与されます。付与日数は勤続年数や労働時間によって決まり、特に年間10日以上付与される場合は、年5日の取得が義務付けられています。取得時期は原則として本人の自由ですが、企業の正常な運営に支障がある場合に限り、会社側が時季変更権を行使できます。企業は、アルバイトを雇用する際に有給休暇の管理を考慮する必要があります。
業務委託とアルバイトの選び方
業務委託とアルバイトのどちらを採用するかは、以下の3つの観点から選ぶことが有効です。
1.業務内容
2.人件費
3.人材育成の経験
これらを考慮することで、自社に適した人材を効率的に採用できます。どちらの雇用形態が自社に合っているか悩んでいる場合は、これらのポイントを参考に検討してみましょう。
1.業務内容
業務内容の専門性が、業務委託とアルバイトのどちらを選ぶかの基準となります。プログラミングやデザインなど、専門的な知識が必要な業務には、即戦力となるプロフェッショナルと業務委託契約を結ぶのが効率的です。一方、接客や軽作業など、多くの人が対応可能な業務であれば、コミュニケーションの取りやすさや人材育成のノウハウ蓄積といった、アルバイト採用のメリットを生かしやすくなります。
2.人件費
人件費を抑えたい場合は、業務委託の活用が有効です。業務委託の場合、仕事がある時だけ依頼し、仕事がなくなれば発注を停止できるため、必要な時だけ人件費をかけることができます。一方、アルバイトを長期で雇うと、雇用契約の打ち切りが難しい上に、残業代や社会保険料など、業務委託にはない人件費が発生します。予算を考慮して人件費を抑えたい場合は、業務委託を検討すると良いでしょう。
3.人材育成の経験
人材育成の観点では、業務委託とアルバイトで大きな違いがあります。業務委託は専門的なスキルを持つプロに依頼するため、業務フローの説明はあっても、特定のスキルを深く教える機会はほとんどありません。一方、アルバイトは業務の進め方から効率的な方法まで幅広く教える必要があり、教育コストがかかります。しかし、この経験を通じて社内に効率的な人材育成ノウハウを蓄積できるメリットがあります。新入社員の育成経験が少ない企業にとって、アルバイト採用は育成ノウハウを培う良い機会となります。
業務委託やアルバイトに関するよくある質問
業務委託とアルバイトの選択に役立つ、よくある質問を解説します。
-
業務委託を採用する際の注意点は?
-
アルバイトとパートに違いはある?
-
アルバイトを業務委託に変更できる?
これらの質問と回答を確認することで、自社に最適な雇用形態を判断しやすくなります。ぜひ、採用前にチェックしておきましょう。
業務委託を採用する際の注意点は?
業務委託を採用する際の最大の注意点は、「偽装請負」にならないようにすることです。偽装請負とは、契約上は業務委託であるにもかかわらず、社員のように働く時間や場所が指定され、作業内容や進め方が細かく管理される状態を指します。
このような状況は、本来対等な立場の業務委託契約から逸脱しており、労働基準法違反と見なされるリスクがあります。偽装請負と判断されると、委託者との間でトラブルに発展する可能性があるため、契約書を明確に作成し、働く時間や場所、業務の進め方について、過度な管理を行わないことが重要です。
アルバイトとパートに違いはある?
アルバイトとパートに法律上の明確な違いはありません。アルバイトはドイツ語の「Arbeit」、パートは英語の「part time」を語源としていますが、どちらも正社員より短い労働時間で働くことを意味します。募集する企業が慣習的に使い分けているに過ぎないため、自社の働き方や募集条件に合わせて使い分けて問題ありません。
アルバイトを業務委託に変更できる?
アルバイトから業務委託への変更は可能です。しかし、人件費削減などの理由で変更する場合は、本人の合意が不可欠です。また、業務委託は雇用契約とは異なるため、業務内容や報酬の支払い方法などを改めて明確にしましょう。業務委託に変更後も勤務場所や時間を会社が一方的に指定すると、偽装請負と見なされる可能性があるため注意が必要です。変更する際は両者がしっかりと内容を理解し、合意のもとで進めるようにしましょう。
業務委託とアルバイトの違いを把握したうえで採用しよう
業務委託とアルバイトは、契約内容や働き方、年末調整の有無など多くの違いがあります。
専門的なスキルを求めるなら業務委託が適していますが、業務の進捗管理や働く時間・場所の指定が難しい場合があります。
一方、アルバイトは社内で雇用するため、細かく指示を出せるのがメリットですが、残業代や社会保険料などの金銭的なコストがかかります。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合わせて採用活動を進めることが重要です。
北海道エリアでの採用活動には、採用管理ツール「ハピキタ」の活用をご検討ください。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。