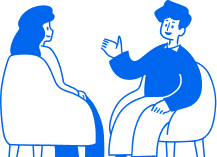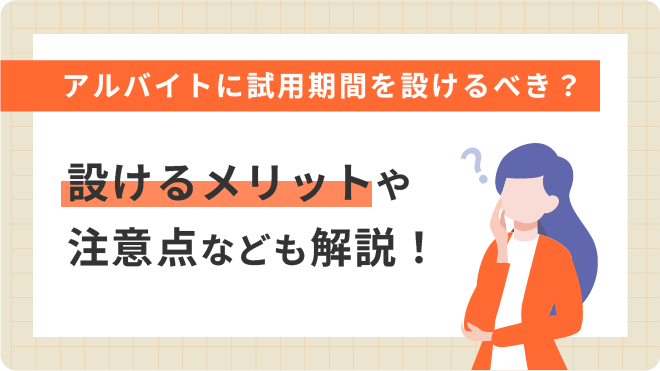
アルバイト採用で「試用期間」を設けるべきか、悩んでいませんか?採用後のミスマッチを防ぎ、人材を見極める上で、試用期間は非常に有効な手段です。この記事では、試用期間を設けるメリットや法的な注意点、よくある質問まで、採用担当者が知っておくべきポイントを解説します。安心して導入するための知識を身に付け、より良い採用活動につなげましょう。
目次
アルバイトに試用期間を設けるべき?
アルバイトの適性を慎重に見極めたいなら、試用期間の導入を検討しましょう。正社員より責任の軽い業務が多いとはいえ、採用後のミスマッチを防ぐ上で試用期間は有効です。企業が試用期間を設けるケースはよくあり、企業だけでなくアルバイトスタッフにとっても、職場への適性を見極める貴重な期間となります。入社後のトラブルを避けるためにも、簡単な業務内容であっても、応募者の適性を見極める期間として活用することをおすすめします。
アルバイトに試用期間を設けるメリット
アルバイトに試用期間を設けることは、採用活動における重要な判断材料となります。これからアルバイトを採用しようと考えている方は、以下の試用期間を設ける主なメリットを理解しておきましょう。
・本採用におけるミスマッチを防止できる
・本採用後の教育の方向性を固められる
本採用におけるミスマッチを防止できる
アルバイトの試用期間は、採用後のミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。ミスマッチとは、企業が求める人材と実際のアルバイトとの間にずれが生じてしまうこと。履歴書や面接だけではわからない、仕事への適性や職場の雰囲気への馴染みやすさを、実際に働いてもらうことで確認できます。これは企業側だけでなく、アルバイト自身が「この会社は自分に合っているか」を判断する機会にもなります。採用や教育にかかったコストを無駄にしないためにも、試用期間は双方にとって有意義な制度です。
本採用後の教育の方向性を固められる
試用期間は、単にスキルや適性を見極めるだけでなく、その後の人材育成計画を立てる上でも重要な期間です。実際に働いてもらうことで、得意な作業や苦手な作業を具体的に把握できます。
試用期間中の情報をもとに、本採用後の教育プランを個別に最適化できるのは大きなメリットです。例えば、特定の作業が苦手だと分かれば、その部分を重点的に指導する研修を計画できます。個々のスキルや特性に合わせた指導方針を確立することで、より効率的かつ効果的な人材育成が可能となり、早期の戦力化につながります。
アルバイトに試用期間を設ける際の注意点
アルバイトの試用期間は、トラブルを未然に防ぐために注意点を押さえることが大切です。特に、以下の3つのポイントを事前に確認しておきましょう。
・本採用後の労働条件と差があるかを説明する
・試用期間から本採用までの流れを説明する
・勤務態度に問題がある場合は入念に指導する
これらの点を押さえることで、採用後のミスマッチや予期せぬトラブルを減らすことができます。
本採用後の労働条件と差があるかを説明する
試用期間中の労働条件を本採用後よりも低く設定すること自体は法的に問題ありません。しかし、応募者が働くかどうかを判断する上で重要な情報となるため、必ず事前に明確に説明する必要があります。
特に、勤務地、給与、シフト、福利厚生といった項目について、本採用時と違いがある場合は、採用面接時や内定通知時に丁寧に伝えましょう。
なお、給与に関しては、試用期間中であっても、各都道府県が定める最低賃金を下回ることは法律で禁止されています。試用期間の給与を本採用後より下げる場合は、必ず最低賃金を下回らないか確認してください。透明性のある情報提供は、入社後のトラブル防止にもつながります。
試用期間から本採用までの流れを説明する
試用期間から本採用までの流れは、企業によってさまざまです。試用期間満了後に自動的に本採用となるケースもあれば、面談や簡単な試験を経て本採用が決定するケースもあります。
アルバイトが安心して入社できるよう、これらの流れは事前にしっかりと説明しておきましょう。特に、面談や試験がある場合は、本採用の可否がいつ頃伝えられるのかも明確にしておくことが大切です。また、試用期間の具体的な期間もあわせて伝えておきましょう。
勤務態度に問題がある場合は入念に指導する
「無断欠勤や遅刻が多い」「上司の指示に従わない」といった勤務態度の問題は、放置すると企業の生産性低下につながります。試用期間は、そうした問題点を早期に発見し、改善を促す重要な期間です。
「なぜ直すべきなのか」「具体的にどうすれば改善できるのか」を明確に伝え、根気強く指導しましょう。 一度で改善が見られない場合でも、繰り返し伝えることが大切です。誠実な指導を通じて、本採用後も円滑に業務を進められるようサポートしましょう。
アルバイトを試用期間中に解雇できる?
アルバイトの試用期間は、正式な雇用に先立って、従業員の能力や勤務態度を評価するために設けられます。法的には「解約権留保付労働契約」と解釈され、通常の労働契約に比べると、客観的に合理的な理由があれば解雇の自由が広く認められる傾向にあります。
しかし、無条件に解雇できるわけではありません。「なんとなく社風に合わない」といった曖昧な理由ではなく、「協調性が著しく欠けている」「度重なる遅刻や無断欠勤がある」「業務遂行能力が著しく不足している」など、客観的に合理的かつ社会通念上相当と判断される理由が必要です。
不当解雇と判断されないためにも、試用期間を設ける際は、どのような場合に解雇が正当化されるか事前に明確にし、解雇を検討する際には慎重に判断することが重要です。
【補足】解雇予告について
解雇予告とは、事業主が従業員を解雇する際、即日ではなく、ある程度の余裕をもって事前にその旨を伝える義務のことです。
企業が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりません。もし予告しない場合は、30日に足りない日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。たとえば、10日前に解雇を伝える場合は、20日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
ただし、試用期間開始から14日以内に解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当は不要とされています。試用期間であっても、働き始めてから14日を超えている場合は、通常通り解雇予告または解雇予告手当が必要になるため注意が必要です。解雇を言い渡す際は、試用期間開始から何日経過しているかを必ず確認し、必要に応じて解雇予告手当の準備を進めましょう。
試用期間中の解雇に正当性が認められるケース
試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。具体的に正当性が認められやすいのは、以下の3つのケースです。
・経歴詐称が発覚した場合
・必要なスキルが著しく不足している場合
・勤務態度が著しく悪い場合
これらを把握しておくことで、万が一の際に解雇の正当性を判断できます。トラブルを避けるためにも、これらのケースを事前に確認しておきましょう。
経歴詐称が発覚した
「経歴詐称」とは、履歴書や面接で伝えた内容に重大な虚偽があったと発覚することです。例えば、保有していない資格や重要な職歴を偽るなど、採用の判断に大きく影響する嘘がこれにあたります。
経歴詐称は、企業の採用活動を阻害する行為であり、発覚した場合は懲戒解雇の正当な理由として認められる可能性が高いです。アルバイトの場合でも、履歴書は入社後も保存しておき、不審な点がないか確認できるようにしておきましょう。
必要なスキルが著しく不足している
採用時に「PCスキル必須」と明記していたにもかかわらず、基本的なパソコン操作もできないなど、求人票で必須とされていたスキルが著しく不足している場合、企業は解雇を検討せざるを得ないことがあります。応募者がスキルを偽って申告しても、採用後に実務で確認すればすぐに分かるため、採用担当者は正直な申告を促すべきです。
一方で、面接時に「入社後にスキルを教える」と伝えておきながら、十分な教育機会を与えずにスキル不足を理由に解雇するのは不当と見なされる可能性があります。スキル不足を理由とした解雇の正当性は、「求人に必要なスキルが明確に記載されていたか」と「入社後の教育体制が十分だったか」の2点が重要な判断基準となります。企業側は、こうした点を踏まえて慎重に対応する必要があります。
勤務態度が著しく悪い
「勤務態度が悪い」とは、正当な理由のない無断遅刻・欠勤を繰り返したり、上司の指示に従わなかったり、同僚と協調性がなくトラブルを起こしたりする状態を指します。
こうした問題行動が見られた場合、企業はすぐに解雇するのではなく、まずは改善を促すための指導を繰り返すことが重要です。注意や指導を何度も行ったにも関わらず改善が見られない場合に限り、解雇の正当性が認められる可能性が高まります。粘り強く指導を行った記録を残しておくことが、万が一のトラブルを避ける上で大切です。
アルバイトの試用期間に関するよくある質問
ここからは、アルバイトの試用期間に関するよくある質問を紹介します。試用期間中の給与や保険、解雇の可否など、細かい疑問を解消することで、より安心してアルバイトを雇用できます。採用活動を始める前に、ぜひ一度ご確認ください。
・試用期間と研修期間はどう違う?
・アルバイトの試用期間はどれくらい?
・試用期間中の退職を申し出られた場合は?
・アルバイトは試用期間中に社会保険へ加入できる?
・アルバイトは試用期間中に有給休暇を取得できる?
試用期間と研修期間はどう違う?
「試用期間」と「研修期間」は似ていますが、目的が異なります。試用期間は、実際に業務を経験してもらい、企業とアルバイトの双方が、雇用契約を継続しても問題ないか判断するための期間です。一方、研修期間は、業務に必要な知識やスキルを教える「教育」が主目的となります。
大きな違いは「業務への着手」です。試用期間は実際に仕事を任せる中で適性を見極めますが、研修期間はあくまで教育が中心となります。ただし、企業によっては両者を明確に区別せず、同じ意味合いで使っている場合もあります。自社の慣習に合わせて、適切に使い分けましょう。
アルバイトの試用期間はどれくらい?
アルバイトの試用期間には法律上の明確な定めはありませんが、一般的には1〜3カ月程度で設定されるケースが多いです。企業によっては、就業規則に基づき6カ月などもう少し長く設ける場合もあります。重要なのは、試用期間の長さを雇用契約書に明記し、応募者に事前に伝えておくことです。勤務態度やスキルに問題が見られる場合は試用期間を延長することも可能ですが、その際も本人にしっかりと理由を説明し、同意を得るようにしましょう。
試用期間中の退職を申し出られた場合は?
試用期間中にアルバイトスタッフから退職の申し出があった場合も、基本的には本採用後と同様に対応が必要です。試用期間は企業だけでなく、働く側にとっても適性を見極める期間であるため、原則として退職の申し出には応じましょう。
法律上は、退職希望日の2週間前までに意思を伝えれば雇用契約は終了できます。ただし、会社の就業規則で「退職の1カ月前までに申し出ること」といったルールを設けることも可能です。
もし急な退職を告げられた場合は、就業規則に則り、アルバイトスタッフと話し合って退職日の調整を進めましょう。退職手続きをスムーズに行うためにも、就業規則の内容を事前に確認しておくことが大切です。
アルバイトは試用期間中に社会保険へ加入できる?
アルバイトであっても、試用期間中に社会保険の加入条件を満たせば、健康保険や厚生年金保険などへの加入義務が生じます。社会保険は雇用形態に関わらず、労働時間や賃金などの要件で加入可否が判断されます。例えば、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合などが一般的な条件です。試用期間中だからといって加入させないのは違法となり、企業が罰則を受けるリスクもあるため、採用の際は事前に加入要件を正確に確認することが重要です。
アルバイトは試用期間中に有給休暇を取得できる?
アルバイトが試用期間中に有給休暇を取得できるかどうかは、働き始めてからの期間によって決まります。年次有給休暇は、「雇い入れの日から6カ月間継続して勤務」し、「その間の全労働日の8割以上出勤」した場合に付与されるのが原則です。
試用期間もこの勤務期間に含まれますが、働き始めて間もない試用期間中では、まだ有給休暇の発生条件を満たしていないことがほとんどです。そのため、基本的に試用期間中に有給休暇を取得することはできません。入社から6カ月が経過し、条件を満たした時点で有給休暇が付与されます。
試用期間中は自社に合った人材であるかをよく確認しよう
この記事では、アルバイト採用における試用期間の重要性や設けるメリット、注意点について解説しました。試用期間は、企業と応募者の双方にとって、採用後のミスマッチを防ぐための大切な期間です。
試用期間中は、応募者が企業の文化や業務内容に馴染めるか、戦力として期待できるかなどをじっくり見極める良い機会です。本採用後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、業務への姿勢やコミュニケーション能力などをよく観察しましょう。
ただし、試用期間中の解雇は、正社員と同様に「客観的に見て合理的な理由」と「社会通念上相当と認められる」正当な理由がないと、不当解雇とみなされる可能性が高いです。解雇は慎重に判断し、安易に行わないようにしましょう。
なお、北海道エリアでのアルバイト採用を効率化したい場合は、採用管理ツール「ハピキタ」の導入をぜひご検討ください。採用活動の負担を軽減し、より良い人材確保につなげることができます。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂 智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。