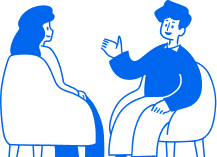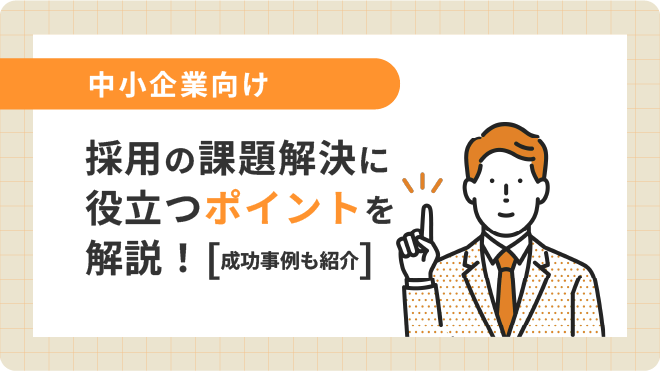
中小企業の採用活動は、大手に比べた労働条件の差や企業認知度の低さなど、さまざまな課題で苦戦しがちです。限られたリソースと資金の中で優秀な人材を確保するには、工夫と戦略が欠かせません。この記事では、採用における失敗の原因から成果をあげるための具体的なポイントまで、成功事例を交えて解説します。思うように人材獲得が進まず悩んでいる採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
中小企業を取り巻く採用の現状
現在、多くの中小企業が採用活動を行っているものの、思うように人材を確保できず、人手不足が深刻化しています。日本商工会議所が2024年9月に実施した調査によると、回答企業2,392社のうち63%が人手不足と回答し、約1,400社がその影響を実感しています。さらに、その6割以上が事業継続や廃業に関わるほど深刻な不足とし、とくに建設業や運輸業では約8割が人手不足を訴えています。
採用活動を強化する企業は全体の約8割に達していますが、解決には至っていません。今後は採用活動に加え、女性・シニア・外国人の活用や、外注・業務のデジタル化による省力化を進める企業が増えていくだろうと言われています。
中小企業が採用活動で苦戦する6つの理由
大手企業に比べ、中小企業が採用で苦戦する理由には以下のような6つの理由が考えられます。
1.売り手市場が続いている
2.知名度が低い
3.条件面で負けている
4.採用の予算が足りない
5.リソースが足りない
6.求人に応募が十分集まらない
1.売り手市場が続いている
日本の採用市場は、長らく続く人手不足が背景にあり、企業にとって厳しい状況が続いています。有効求人倍率を見ても、2025年7月時点で1.22倍と、求職者数よりも求人数が多い「売り手市場」であることがわかります。
また、少子高齢化によって日本の労働人口は、2030年以降、減少に転じると予測されており、人材獲得競争はさらに激化するでしょう。実際に、2024年3月卒の大学生の就職率は98.1%と過去最高を記録しており、求職者は「選ぶ側」の立場にあります。
このような状況下で、知名度の低い中小企業が優秀な人材を確保するためには、「この会社で働きたい」と思わせるような独自の魅力を効果的に発信していくことが不可欠です。
2.知名度が低い
中小企業が採用で苦戦する大きな要因のひとつに「知名度の低さ」があります。自社の存在を知られていなければ、求人への応募そのものが伸びにくいのは当然です。大企業はTVCMやWeb広告、スポーツ選手へのスポンサー活動などを通じて認知度を高め、学生やビジネスマンに企業名や事業イメージを浸透させています。そのため、応募者は自然と知名度のある企業の選考を優先する傾向があります。とくに一般消費者と接点の少ないBtoB企業は、BtoC企業に比べ認知されにくいのが実情です。新卒・中途を問わず、まずは自社を知ってもらう取り組みが採用成功の第一歩となります。
3.条件面で負けている
求職者が企業を選ぶ際に注目する条件には、給与、各種手当(家賃補助・資格手当など)、賞与、年間休日数、福利厚生、研修体制といった要素があります。新卒・中途を問わず、条件が整った企業を優先するのは自然なことです。近年は物価高や奨学金返済といった金銭的な不安を背景に、大企業が賃上げに踏み切る例も増えていますので、中小企業も同様の対応が求められています。もちろんすべてを大手と同等に整えるのは難しいですが、最低でも1つは「強み」と言える条件を持たなければ、求職者の関心を引くことは困難です。
4.採用の予算が足りない
採用活動には、説明会の開催や就職イベントへの参加、求人広告の掲載など、様々な費用が発生します。一般的に、新卒採用の選考全体にかかる費用は数百万円規模に及ぶことが多く、入社予定者一人あたりにかかる費用も数十万円と言われています。大手企業は潤沢な採用予算を確保できますが、中小企業はそうはいきません。採用活動にかけられる予算が限られているため、「いかに無駄なく優秀な人材を確保できるか」が重要な課題となります。この予算の制約により、大企業のように大規模なイベントや多様な求人メディアを活用することが難しく、求職者への露出機会が減ってしまうのが現状です。
5.リソースが足りない
中小企業では、人事と労務を1人の担当者が兼任しているケースも珍しくありません。研修企画や勤怠管理、給与計算など多岐にわたる業務をこなすなかで、採用活動に十分な時間や労力を割けないのが現実です。その結果、採用戦略や求める人物像の設計、評価基準の明確化といった重要な検討が後回しになりがちです。従来型の方法に頼らざるを得ず、成果が出にくいだけでなく、採用ノウハウも蓄積されない悪循環に陥ってしまいます。
6.求人に応募が十分集まらない
会社説明会の開催回数や就職メディアでの掲載枠が限られると、応募者が自社を知る機会は減少します。さらに、採用担当者がリソース不足で多忙な場合、応募が集まらない原因を正確に分析できないリスクも高まります。求人サイトや人材紹介会社に数多く掲載しても、知名度が低ければ求職者に魅力が伝わりにくく、結果として理想とする人材に出会える確率は低くなります。中小企業にとっては「応募数の確保」自体が大きなハードルなのです。
【中小企業編】採用活動の課題を解決するためのポイント
では、実際に採用活動を行う中で解決に向けてできることにはどんなことがあるでしょうか。以下のポイントで解決策を紹介します。
・求人に応募が集まらない理由を分析する
・採用ターゲットとペルソナを決めておく
・待遇の相場を把握して見直しを行う
・採用サイトで情報を発信する
・SNSを活用する
・社員と交流できる場を作る
・採用管理システムを導入する
求人に応募が集まらない理由を分析する
応募が集まらない場合、まずはその原因を冷静に分析することが必要です。例えば、採用サイトがない、コーポレートサイトの更新がほとんど行われていない、SNSアカウントがないといった状況では、求職者は企業の情報を得られず不安を感じます。特にコーポレートサイトが数年間更新されていない場合、「人手不足で余裕がない」「経営が安定していない」といったネガティブな印象を与え、応募をためらわせる可能性が高いでしょう。
また、求人メディアの選定ミスも大きな要因です。メディアによって「新卒に強い」「地元求人に特化」など特徴が異なるため、自社の採用ターゲットに合った媒体を選べているか確認が必要です。さらに、求人情報に待遇や仕事内容の記載が不足していたり、相場より条件が低い場合も応募数が減る原因となります。こうした要素を一つずつ洗い出し、改善していくことが、応募者増加への第一歩です。
採用ターゲットとペルソナを決めておく
効果的な採用活動には、採用ターゲットと採用ペルソナを明確にすることが欠かせません。採用ターゲットとは、求めるスキルや経験年数など、応募条件に合致する人材を広く定義したものです。
一方で採用ペルソナは、自社にとって理想的な架空の人物像を設定することを指します。職歴や価値観、保有スキルといった具体的な要素を盛り込み、テンプレートを使って整理すると設定しやすくなります。ペルソナを明確にすることで「どんな人物を採用したいか」がはっきりし、書類選考や面接の基準がぶれにくくなります。その結果、公平な評価を行いやすくなり、採用のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
待遇の相場を把握して見直しを行う
応募が集まらない要因のひとつに、待遇面で競合他社に劣っていることが挙げられます。給与が明らかに低かったり、年間休日数が少なかったりすると、求職者が魅力を感じにくいのは当然です。まずは民間の就職・転職サイトを活用し、同業他社がどのような条件で人材を募集しているかを調査し、相場を把握することが重要です。そのうえで、給与の引き上げや休日数の増加を検討する必要があります。
ただし、必ずしも給与面の改善が可能とは限りません。その場合は在宅勤務や時短勤務の導入、保育園費用の補助、スキルアップを支援する研修制度の充実など、別の魅力を発信する方法があります。求職者の価値観は多様であり、すべての人が給与や休日数だけで企業を選ぶわけではありません。自社ならではの強みをアピールすることで、応募意欲を高められるでしょう。
採用サイトで情報を発信する
求職者が応募をためらう背景には、自社で働くイメージが描けないことがあります。採用サイトがなければ、コーポレートサイトや求人票に記載された限られた情報しか提供できず、他社と比べて不利になる可能性があります。求職者は応募前に複数の情報源を参考にし、働きやすさを確認したり、求める人物像と自分自身が合致しているかどうかを判断しています。採用サイトを設けることで、社員インタビュー動画やオフィス写真といったリアルな情報を発信でき、応募数の増加や採用ミスマッチの防止につながります。
SNSを活用する
SNSは拡散力に優れたツールなので、求職者に役立つ情報を発信すればシェアやリポストを通じて手間をかけずに情報が広まります。多くのSNSは無料で利用でき、費用負担も小さい点が魅力です。写真や動画を交えることで、社員の働く様子や社内の雰囲気、柔軟な働き方などをリアルに伝えられるため、自社の魅力を効果的にアピールすることもできるでしょう。
ただし、SNSは短期間で成果が出にくいため、長期的な視点で取り組むことが重要です。また、投稿内容や表現には細心の注意を払い、誤解を与えない情報発信を心がける必要があります。
社員と交流できる場を作る
採用活動において、求職者と気軽に接点を持てる「カジュアル面談」を取り入れる企業が増えています。これは選考ではなく、応募書類の提出も不要なため、求職者にとって参加のハードルが低い点が特徴です。さらに職場見学や先輩社員との座談会と組み合わせることで、求人票や採用サイトでは伝わりにくいリアルな情報を提供でき、求職者の満足度も高まります。企業側にとっても、優秀な人材や転職を検討中の潜在層と接点を持てる貴重な機会となり、選考前から相互理解を深めることでミスマッチ防止にもつながります。工数が気になる場合は、双方にとって負担も少ないオンライン面談から始めると良いでしょう。
採用管理システムを導入する
採用業務を効率化するには、採用管理システムの活用が有効です。主な機能としては以下のようなものがあります。
・求人票の作成と管理
・求人サイト・転職エージェントとの連携
・応募者情報・提出書類の管理
・選考状況の可視化
・面談日程の自動調整
・採用サイトの制作
・内定者管理
・メールの自動送信
システムを導入することで、応募者の進捗状況をリアルタイムで確認でき、採用担当者が複数いる場合でも情報共有がスムーズになります。さらに、求人サイトとの連携や面談調整といった手間のかかる業務を効率化できるため、採用担当者の負担を大幅に減らし、戦略的な採用活動に時間を割けるようになります。
採用業務を効率化するなら『ハピキタ』
採用業務を効率化したいなら、北海道アルバイト情報社が提供する採用管理システム『ハピキタ』がおすすめです。Indeedなどの求人サイトや求人ボックスなどの求人検索エンジンに自動で求人を投稿できるほか、北海道の求人に特化した「アルキタ」や「ジョブキタ」にも対応しています。北海道で50年以上求人を取り扱ってきた実績がある当社ならではのノウハウを活用できる点も大きな強みです。
さらに採用サイトの立ち上げ機能を備えており、自社の魅力や採用情報を幅広く発信できます。写真撮影や記事内容の提案は、取材をもとに運営側が対応するため、手間をかけずに質の高い採用サイトを制作可能です。求人は少なくとも月10件まで掲載でき、継続的な採用活動にも適しています。中長期で人材を確保したい場合や募集データを多く扱う企業にとって、『ハピキタ』は心強い選択肢となるでしょう。
【ジョブキタ就活とハピキタで採用成功】中小企業の採用事例2選
ここでは、ジョブキタ就活やハピキタを使い、採用に成功した中小企業の採用事例を紹介します。課題解決のポイントを具体的に見ていきましょう。
65歳以上が40%の町で新卒採用者を獲得 | 天塩川工業株式会社
天塩川工業株式会社は、林業と建設業を営む企業です。人口の40%以上が65歳以上の北海道中川郡中川町に拠点を置いており、以前は中途採用を主に行っていました。しかし、林業の専門性を理解してもらうことに苦労していました。そこで、新卒採用に切り替えることを決意し、就活サイト「ジョブキタ就活」を活用しました。取材をベースに制作された求人原稿と会社ホームページには、企業の魅力はもちろん、町の魅力もふんだんに盛り込まれていました。その結果、4名の学生から応募があり、自然豊かな環境での仕事に魅力を感じた学生の内定が決定。内定後も定期的な情報発信や、交通費を負担しての職場見学など、学生に寄り添った丁寧な対応が功を奏し、内定承諾へとつながりました。この成功を受け、今年も新卒採用を継続する予定です。
採用管理システムの導入で求人への応募数が3割増加 | 株式会社ニスコ
小学生から高校生までを対象に学習塾を運営する株式会社ニスコでは、集団指導に加え少人数指導にも注力しており、アルバイト・パート講師の確保が欠かせませんでした。従来は欠員が出るたびに求人を掲載していましたが、倶知安や音更など人口の少ない町では人材確保が難しく、採用コストがかさむという課題がありました。さらに小学生向け授業では早い時間帯に勤務できる講師も必要でした。そこで採用管理システム「ハピキタ」を導入。常時募集が可能になったことで応募数は2〜3割増加し、地方拠点でも安定的に採用を実現しました。あわせて採用コストも2〜3割削減に成功し、効率的な採用活動につながっています。
中小企業が採用活動で成果を出すためのポイントを理解しておこう
中小企業の採用活動は、知名度の低さやリソース不足など、多くの課題を抱えています。求める人材を確保するためには、まず自社の弱点を正確に把握することが重要です。その上で、社員インタビューや職場紹介といった定期的な情報発信、社員との交流イベントなどを通じて、企業の魅力を積極的に伝えましょう。
また、採用業務の負担を軽減し、効率を高めるためには、「ハピキタ」に代表される採用管理システム(ATS)の導入が非常に有効です。これにより、応募者情報の管理や選考プロセスの進捗管理がスムーズになり、採用担当者の負担を大幅に減らすことができるでしょう。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂 智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。