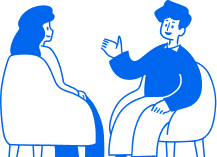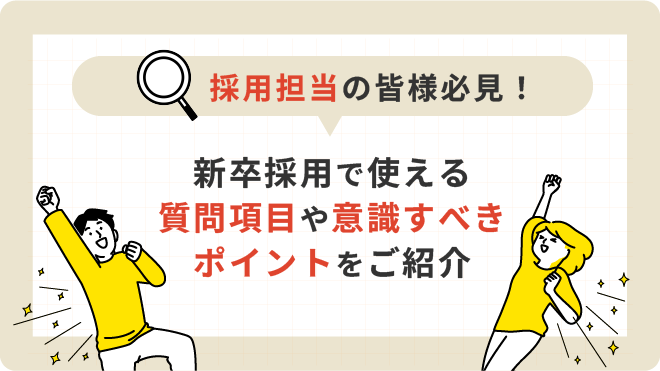
少子高齢化の影響で売り手市場が続いており、自社が求める人物像に合致した学生を採用するのは年々難しくなっています。
そんな中、新卒採用の面接では、学生の志望度や自社との相性、企業や職種への理解度など、さまざまな面を限られた時間で判断しなければなりません。では、面接では具体的にどのような質問を投げかけるべきでしょうか。
本記事では、新卒採用の面接で使える質問内容や意識すべきポイントなどを紹介します。新卒採用を担当している方は、最後までご覧ください。
新卒採用での面接手法3選
新卒採用での面接手法には大きく分けて3つあります。それぞれの手法にはメリットデメリットもあるので、まずはその特徴を確認しましょう。
個人面接【対面型】
対面型の個人面接は、応募者1人に対し、面接官が1~3人で実施する形式です。直接対話できるため、学生の人柄や仕事に対する価値観、志望度を深く掘り下げられます。学生も落ち着いて臨めるため、本来の力を発揮しやすく、自社との相性をじっくりと見極められる点が大きなメリットです。一方で、オンラインでの個人面接や集団面接と比べて1人あたりの面接時間が長くなるため、手間がかかります。また、面接官によって評価にばらつきが出ないよう、事前に評価基準をすり合わせるトレーニングが不可欠です。
個人面接【オンライン型】
オンライン型の個人面接は、学生1人に対し、面接官が1~2人でオンラインで実施する形式です。自宅から面接を受けられるため、学生は移動の負担がなく、企業側も1日に多くの面接を実施できるため、選考をスピーディーに進められる点が大きなメリットです。一方で、通信環境によって面接が中断したり、質問の意図や表情、熱意が伝わりにくかったりするデメリットもあります。対面よりもコミュニケーションが難しい側面があるため、面接官は質問の言葉選びや、学生の発言を丁寧に引き出す工夫が求められます。
集団面接
集団面接は、2〜5人程度の学生に対し、面接官が1〜3人で行う形式です。一度に複数の学生を評価できるため、選考効率がよく、書類選考の次に実施されることが多いです。学生同士を比較できるため、評価しやすいというメリットがあります。一方、学生一人ひとりと向き合う時間が短く、学生の潜在能力や個性を深く見極めるのは困難です。また、回答の順番や他の学生のレベルによって評価が左右されるなど、必ずしも公平な評価ができるとは限りません。面接官のスキルによって、学生の力を十分に引き出せない可能性があることもデメリットと言えるでしょう。
新卒採用の面接で使える質問例
学生の緊張をほぐし、本音を引き出すための質問は、面接の成否を左右します。ここでは、面接の流れに沿って使える質問例をパターン別に紹介します。
面接官の自己紹介
面接の冒頭では、学生の氏名を確認した上で、「□□さんですね。本日はお時間をいただきありがとうございます。人事部採用担当の○○です。本日はどうぞよろしくお願いいたします」というように、応募への感謝の気持ちを混じえて挨拶をしましょう。丁寧な自己紹介は、学生に安心感を与え、企業の印象を良くする効果があります。学生の緊張を和らげ、この後のコミュニケーションを円滑に進めるためにも、礼儀正しい第一歩を大切にしましょう。
アイスブレイク
アイスブレイクは、学生の緊張を和らげ、スムーズなコミュニケーションを促すために不可欠です。特に新卒の学生は、自身の将来を左右する面接に、強いプレッシャーを感じています。本音や人柄を引き出すには、場を和ませることが大切です。面接を始める前に、ごく簡単な雑談を挟むことで、学生は本来の力を発揮しやすくなります。質問は「はい」か「いいえ」で答えられるクローズド・クエスチョンが効果的です。たとえば、「最寄駅から迷わず来られましたか?」「部屋の温度は問題ありませんか?」、オンライン面接であれば「音声や映像に問題はありませんか?」といった質問で、学生の緊張をほぐしましょう。
学生の自己紹介
「○○さんの自己紹介を1分程度でお願いします」と切り出し、本格的に面接に入ります。自己紹介は、自己分析や事前準備の度合いが測れる重要な機会です。また、仕草や声のトーン、言葉遣いや話すスピードを通し、基礎的なマナーや第一印象、人柄を知ることもできます。時間制限を設けることで、学生のコミュニケーション能力や要約力を確認することもできます。
学生のスキルや経験に関する質問
学生がこれまでの経験から何を得てきたかを知ることは、潜在能力を見極める上で重要です。面接では、エントリーシートの内容を深掘りする形で質問を投げかけましょう。例えば、「学生時代に最も頑張ったことは何ですか?」や「学生生活で得た学びを仕事にどう生かせますか?」といった質問が有効です。学業や資格取得に注力した学生には、具体的な研究内容や、目標達成に向けた学習方法を尋ねることで、物事を深く突き詰める力や計画的に取り組む姿勢をうかがうことができます。
学生のパーソナリティに関する質問
学生の強み・弱みを尋ねることで、自己分析の深さと客観性を見極められます。自分を客観的に評価できる人は、入社後も自身の強みを仕事に生かし、弱みを補うための努力を冷静に考えられるため、成長する可能性が高いと言えます。「あなたの強みは何ですか?その強みが発揮されたエピソードを教えてください」や、「ご自身の弱点は何だと思いますか?弱点を克服した経験があれば教えてください」といった質問を通して、学生がどのように困難を乗り越え、周囲と協力して目標を達成してきたかを知るヒントが得られます。
志望動機に関する質問
志望動機は、学生の入社意欲や自社との相性を見極めるための重要な質問です。面接では、結論から話し、具体的なエピソードを添え、入社後にどう貢献したいかを明確に答えられているかを確認しましょう。話の構成が曖昧だったり、エピソードの具体性に欠けていたりする場合、自社への志望度が低いと判断できます。「弊社の求人に応募した理由を教えてください」や「希望職種とご自身が合っていると感じた理由を教えてください」といった質問で、自社への理解度を測ります。さらに、「この業界に興味を持った理由を教えてください」や「業界全体の課題は何だと思いますか?」といった質問をすることで、業界への関心度や深い思考力を探るのも有効です。
仕事の価値観を確認する質問
仕事に対する価値観は、自社の社風に合うかどうか、さらに学生がどのような環境で力を発揮し、長く活躍できるかを見極める重要なヒントになります。「仕事をするうえで、どのようなことを大切にしたいですか?」と尋ねることで、学生が何を重視して働くか、その背景にある具体的な行動傾向を可視化できます。例えば、「誠実さ」を重視する人は、信頼関係を築く丁寧なコミュニケーションを求めていることがわかりますし、「挑戦」を大切にする人は、困難な状況でも積極的に取り組む姿勢を持っていることがわかります。一方で、「真面目に働く」や「コミュニケーションを大切にしたい」といった抽象的な回答は、熱意や思考の深さが見えにくいため、さらに深掘りする質問を重ねることが有効です。
コミュニケーション能力に関する質問
仕事は、社内外のさまざまな人との連携で成り立っています。学生時代とは異なり、苦手なタイプの人とも協力して業務を進める場面は少なくありません。学生が周囲の人とどのように関わってきたかを知ることで、入社後のコミュニケーション能力や協調性を予測できます。「チーム内で意見が対立した経験はありますか?その際、どのように対応しましたか?」や「初対面の人と接する場面では、どのように振る舞うことが多いですか?自分から積極的に声をかけるタイプですか?それとも、まずじっくりと観察するタイプですか?」といった質問から、学生が周囲にどのように働きかけ、課題を解決してきたか、また、他者との関係構築においてどのような姿勢を持っているかを探りましょう。
ストレス耐性に関する質問
ストレス耐性は、困難な状況でも冷静に対応する力で、早期離職を防ぐ上では非常に重要です。優れたスキルを持っていても、ストレス耐性が低いと、予期せぬトラブルや人間関係で壁にぶつかった際に離職するリスクが高まります。面接では、学生がストレスをどのように感じ、対処してきたかを確認することが大切です。ただし、「ストレス耐性」という言葉をそのまま使うと、ネガティブな印象を与えかねません。質問の言葉選びには細心の注意を払いましょう。「これまで何か不安や緊張を感じたり、ストレスが原因でうまくいかなかった経験はありますか?また、その不安や緊張にどのように対処しましたか?」といった質問で、学生の対処法や考え方を探るのが効果的です。
新卒採用を成功させるためのポイント
新卒採用を成功に導くには、面接の質を高めるだけでなく、採用活動全体を見直すことが重要です。ここでは、欲しい人材を獲得するために押さえるべきポイントを5つご紹介します。
1.長期的な視点で採用活動を行う
少子高齢化や人手不足の影響で、新卒採用は学生優位の「売り手市場」が続いており、採用活動は年々難易度を増しています。内定を出しても辞退される可能性も高く、通年採用で長期的に学生を募集する企業も増えています。
例えば、アルティウスリンク株式会社では、学生の内定辞退を前提に、ジョブキタ就活を活用しながら春から冬まで通年で採用活動を行っています。これにより、部活動に打ち込んでいた学生や公務員志望から民間企業へ切り替えた学生など、多様な人材に出会えるチャンスが生まれました。また、全国規模から地域特化型まで、複数の求人メディアを使い分けることで、より多くの学生にリーチできるよう工夫しています。
新卒採用は、長期的な視点と柔軟な戦略で採用機会を広げることが重要です。
2.学生が答えやすい雰囲気づくりに努める
学生がリラックスして面接に臨めるよう、面接官は雰囲気作りに注力しましょう。緊張感がある場では、学生は本来の自分や入社への熱意を十分に伝えられません。面接官は、学生の目をしっかり見て相槌を打ち、話に耳を傾ける姿勢が求められます。
また、客観的な視点で評価できるよう、面接前に面接トレーニングを実施するのも有効です。動画視聴やロールプレイング、専門家への依頼など、さまざまな方法でトレーニングを行い、学生の潜在能力を最大限に引き出せる面接を目指しましょう。
3.共通の質問を用意しておく
面接の評価を客観的に行うため、共通の質問項目を事前に用意しておきましょう。これにより、複数の学生の回答を比較しやすくなり、スキルや人柄、志望度を公正に評価できます。多くの企業で採用されている「自己紹介・自己PR」「学生時代に力を入れたこと」「志望動機」「長所・短所」といった質問は、学生も準備していることが多く、彼らが最も伝えたいことを引き出すのに有効です。同じ質問を投げかけることで、学生一人ひとりの個性をより明確に把握し、自社に合った人材を見つけ出す精度が高まります。
4.身だしなみやマナーも評価対象に
学生の身だしなみやマナーは、一緒に働きたいと思える人物か、第一印象を判断する重要な要素です。スーツが体のサイズに合っているか、清潔感があるか、明るい表情で話せるかといった点を確認しましょう。また、質問に対する声の大きさや、敬語を適切に使えているか、挨拶がきちんとできるかなども、評価のポイントに含まれます。ただし、これらの項目をどの程度評価に含めるかは企業や職種によって異なるため、面接官同士で事前にすり合わせを行い、評価基準を明確にしておくことが大切です。
5.内定後も手厚くフォローする
新卒採用では、内定から入社まで半年以上の期間が空くことも珍しくありません。時間が経つにつれて「本当にこの会社で良いのか」と不安に感じたり、他の企業から好条件のオファーを受けて内定を辞退する学生も少なくありません。
内定辞退を防ぐには、学生と定期的に連絡を取り合い、不安を取り除くことが大切です。例えば、北海道中川郡で林業を営む天塩川工業株式会社では、毎月現場の様子を写真付きでメール送信したり、交通費を全額負担して会社へ招き、職場や住居の案内を行うなど、手厚いフォローを実施しています。こうした取り組みは、企業側の受け入れ態勢をアピールし、内定者の入社に対する安心感を高める上で有効です。内定後も継続してコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことで、内定辞退のリスクを軽減できます。
新卒採用の面接で尋ねるべき質問やポイントを理解しよう
新卒採用を成功させるには、学生の潜在能力や入社意欲を見極める質問が不可欠です。面接では、学生時代に力を入れたことや志望動機、パーソナリティに関する質問を通して、学生の熱意や自社への理解度を深く掘り下げましょう。また、内定辞退のリスクを考慮し、通年採用や内定後の手厚いフォローなど、長期的な視点で採用活動に取り組むことが重要です。この記事では、新卒採用を成功させるための面接での質問例や、内定辞退を防ぐための長期的な取り組みについて解説しました。これらのポイントを押さえることで、貴社に貢献してくれる最適な人材の獲得に繋がるでしょう。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂 智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。