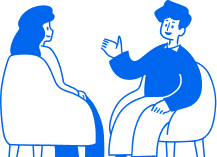採用活動において、企業と求職者間のミスマッチを防ぐことは、早期離職の防止と優秀な人材の定着に直結する最重要課題です。特に、キャリアの選択に不慣れな新規学卒者や、将来の安定を求める若年層の求職者にとって、企業の実態を示す情報は極めて重要です。
この背景から、日本では「若者雇用促進法」(青少年の雇用の促進等に関する法律)に基づき、企業が一定の職場情報、とりわけ「離職者数」といった就労実態に関する情報を応募者からの求めに応じて提供することが義務付けられています。
今回は、応募者からの質問、特に「離職者数」に関する質問に企業がどのように対応すべきか、法的義務の範囲と、採用活動の成功に繋がる情報開示の戦略について、詳細に解説します。
応募者から「離職者数」を聞かれたら?
情報提供の義務とその対象者
結論として、就職活動中の学生や若年層の転職者など、応募者から「過去3年間の離職者数は何人ですか?」といった質問があった場合、企業には情報を提供する義務が発生します。
この義務は、特に新規学卒者や35歳未満の若年層の転職者を募集・採用する場合に適用されます。これは、若者雇用促進法が、これからの社会を支える若い世代が不安定な就労を繰り返すことを防ぎ、安定した職業生活を送れるよう支援することを目的としているためです。
義務の根拠と目的
若者雇用促進法は、単に「労働条件」を正確に伝えるだけでなく、求職者がその職場で実際にどのように働き、成長できるのかを具体的にイメージできるようにするため、職場情報の提供を義務付けています。この義務の背後には、以下の重要な目的があります。
-
雇用の安定:求職者が労働条件や職場環境を的確に把握することで、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぎ、早期離職を未然に防ぎます。
-
労働市場の透明性の向上:企業が自社の実態を隠さずに開示することで、求職者は安心して応募先を選択でき、労働市場全体の信頼性が向上します。
年齢に関わらない望ましい姿勢
若者雇用促進法が定める義務の対象は若年層ですが、企業が長期的に安定した雇用を維持するためには、年齢や雇用形態にかかわらず、すべての応募者に対して正確な情報を提供することが強く望まれます。
情報開示は、単なる法的な義務の履行ではなく、企業の誠実さを示す行為であり、応募者との間に信頼関係を築くための第一歩です。積極的に透明性を確保することで、応募者の安心感を高め、結果的に企業文化や価値観に深く共感する質の高い人材の獲得につながります。
具体的にはどこまで回答しなくてはならないのか
応募者(特に若者雇用促進法の対象者)から就労実態等に関する質問があった場合、企業は「採用状況」「職業能力開発」「雇用管理」の3つのカテゴリ(ア)〜(ウ)それぞれについて、少なくとも1つ以上の情報を提供しなければなりません。
離職者数に関する質問は、この情報提供義務の中核となる項目です。
(ア)募集・採用に関する状況(離職者数を含む)
このカテゴリは、応募者が最も関心を寄せる「安定性」と「公平性」に関わる情報を提供します。
|
情報項目 |
焦点となる関心事 |
|
過去3年間の新卒採用者数と離職者数 |
組織の定着率。離職率の高さは職場環境の課題を示すシグナルと捉えられるため、企業は最も正確な情報開示が求められる。 |
|
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 |
採用における男女公平性、多様な人材の受け入れ状況。 |
|
平均勤続年数(可能であれば平均年齢も) |
組織全体の安定性、キャリア形成の長さ、従業員の年齢構成。 |
「離職者数」は、このカテゴリの中でも特に重要な項目です。質問された場合は、新卒採用者に限定せず、可能な範囲で中途採用者も含めた全体像を伝えることが、より誠実な対応となります。
(イ)職業能力の開発・向上に関する状況
このカテゴリは、応募者が「入社後の成長」と「キャリア形成」を判断するために必要な情報です。
|
情報項目 |
焦点となる関心事 |
|
研修の有無と内容 |
企業が従業員の成長にどれだけ投資しているか、具体的なスキルアップの機会。 |
|
自己啓発支援の有無と内容 |
従業員の自発的な学びをサポートする制度(例:資格取得費用補助、通信教育受講支援など)。 |
|
メンター制度の有無と内容 |
新入社員の精神的なサポート体制、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)以外の支援体制。 |
|
キャリアコンサルティング制度の有無と内容 |
長期的なキャリアプランの相談機会、将来の展望を描くための支援体制。 |
|
社内検定制度の有無と内容 |
社内でのスキル評価基準、専門性向上のための具体的な目標設定の有無。 |
これらの情報を通じて、企業が単に人を雇うだけでなく、「人を育てる」ことに対して積極的である姿勢を示すことができます。
(ウ)企業における雇用管理に関する状況
このカテゴリは、「ワークライフバランス」と「働きやすさ」を判断するための実態情報です。
|
情報項目 |
焦点となる関心事 |
|
前年度の月平均所定外労働時間の実績 |
実際の残業時間。過重労働の有無、効率的な働き方への取り組み状況。 |
|
前年度の有給休暇の平均取得日数 |
休暇の取得しやすさ、従業員の休息の確保状況。 |
|
前年度の育児休業取得対象者数と取得者数(男女別) |
育児と仕事の両立支援体制、特に男性の育児参加に対する企業の理解度。 |
|
役員に占める女性の割合と管理的地位にある女性の割合 |
女性の活躍推進状況、ガラスの天井の有無、昇進機会の公平性。 |
特に「所定外労働時間」や「有給休暇取得日数」は、求職者が最も実態を知りたいと考える情報であり、正確な開示が企業の信頼性を高めます。
就労実態等に関する情報を提供するときの注意
1. 不利益な取り扱いの絶対禁止
最も重要な注意点は、応募者が質問を行ったという事実を理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならないということです。これは若者雇用促進法において明確に禁止されている行為です。
<不利益な取り扱いの具体的な例>
情報提供を求めた応募者に対してのみ、説明会や面接などの採用選考に関する情報を意図的に提供しない。
面接の場で、「あなたは離職者数について質問してきたが、それは当社への忠誠心がない証拠ではないか」といった形で、情報提供を求めた事実に触れ、選考の判断材料とすること。
質問は、応募者が入社後の人生設計を真剣に考えている証であり、企業はその姿勢を尊重し、公平な選考を行う義務があります。
2. 情報の正確性と最新性
提供する情報は、必ず最新かつ正確なものでなければなりません。あいまいな情報や誇張された数字、または実態と異なるデータを開示することは、たとえ悪意がなくても「虚偽の記載」と見なされ、応募者の信頼を大きく損ない、早期離職の根本原因となります。
データは社内の人事部門や労務管理部門と連携し、客観的な根拠に基づいて算出し、説明責任を果たせる状態で保管しておくことが必要です。
3. プロアクティブな情報開示の推奨
応募者からの質問を待って受動的に回答するだけでなく、積極的に情報を開示することが、現代の採用活動では推奨されます。
企業ウェブサイトや採用パンフレットでの公開:若者雇用促進法で定められた情報(ア〜ウ)を事前に公開しておくことで、応募者の信頼感が向上し、「隠し事がない」というポジティブな企業イメージを構築できます。
説明会での一括説明:応募者説明会などで、これらの情報を一括して提供することで、個別の質問対応の手間を減らしつつ、すべての応募者に対して公平な情報を提供できます。
プロアクティブな開示は、採用プロセスをスムーズにし、透明性の高い企業文化をアピールする絶好の機会となります。
まとめ:採用成功の第一歩は情報開示の積極性
応募者から「離職者数」に関する質問があった場合、新規学卒者や若年層を対象とする募集・採用においては、企業は法的に情報提供の義務を負います。この義務は、若者雇用促進法に基づき、採用状況、職業能力開発、雇用管理の3つの分野にわたる具体的な情報に及んでいます。
情報開示は、単なる法令遵守の義務に留まりません。
採用活動における成功の第一歩は、自らの応募者への情報開示の積極性にあります。企業が正確な実態を包み隠さず伝えることで、応募者は納得感をもって入社を決意でき、結果として企業文化にフィットした人材の定着率が向上します。
年齢や雇用形態にかかわらず、応募者からの質問には可能な限り誠実に回答し、「質問を行ったこと」を理由とする不利益な取り扱いは絶対に行わないという姿勢を貫くことが、信頼される企業として採用市場で勝ち抜くための不可欠な戦略となります。

Writer
ヒトキタ編集部 山本祥子
Profile
コンテンツメディア部にてユーザー向け施策の企画・サイト運営に従事。フリーペーパー編集などを手掛け、現在は広報・販促・営業支援・デザインを行う。