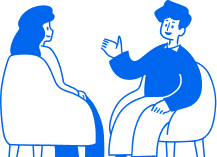「採用コストが膨らんでいる」「広告費をかけても応募が来ない」—これは、特に限られた予算と人員で採用活動を行う中小企業の人事担当者様が抱える、共通の、そして深刻な悩みではないでしょうか。
少子高齢化が進む現代の採用市場は、多くの業界で「売り手市場」が常態化しており、競争は激化の一途をたどっています。非効率な採用活動に陥り、費用だけがかさんでしまうケースは少なくありません。
しかし、採用コストの削減は、単に経費を切り詰めるだけの話ではありません。それは、自社の採用活動を戦略的に見直し、「優秀な人材が定着し、より良い組織を作るための土台を築く」ための、非常に重要な第一歩です。
本記事では、採用コストの基本的な内訳から、コストが高騰してしまう根本原因、そして自社ですぐに始められる具体的な削減方法10選、さらには失敗しないための注意点までを、分かりやすく解説します。
採用活動の無駄を徹底的に排除し、限られた予算内で最大の効果を出すための戦略を、一緒に考えていきましょう。
目次
そもそも採用コストとは?
採用コストの削減に取り組む前に、まず「何に」「いくら」費用がかかっているのかを正確に把握する必要があります。費用を正確に把握せずに削減に着手することは、やみくもに経費を削るだけで、かえって採用活動の質を低下させるリスクがあります。
まずは、採用活動にかかる費用の基本的な内訳と、新卒・中途採用それぞれのコスト構造について解説します。
採用コストは「外部コスト」と「内部コスト」に分けられる
採用活動にかかる費用は、大きく「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に大別できます。
外部コスト
社外へ支払いが発生する費用、すなわち「採用活動を行うために外部のサービスやリソースを利用する費用」です。
具体的な項目:
求人広告費(求人サイト、新聞、雑誌などへの掲載料)
人材紹介会社への成功報酬(エージェントフィー)
採用イベント(合同企業説明会など)への出展費
採用関連ツール(適性検査、Web面接システムなど)の利用料
採用パンフレットや動画などの制作費用
内部コスト
社内で発生する費用、すなわち「採用活動に関わる人件費や社内リソース利用にかかる費用」です。外部に支払う費用ではありませんが、工数として考慮すべき重要なコストです。
具体的な項目:
採用担当者や面接官の人件費・残業代
内定者フォローにかかる費用(懇親会費、交通費、資料作成費など)
面接会場の準備・維持費用(会場費、備品費など)
社員が採用活動に協力した場合のインセンティブや謝礼
入社手続きや研修準備にかかる人件費
自社の採用単価を計算する方法
自社の採用コストが適正な水準にあるかを知るために、まずは「採用単価」を計算することを推奨します。
採用単価の計算式
採用単価を算出する基本的な計算式は以下の通りです。
採用単価=(外部コストの総額)+(内部コストの総額)÷採用人数
例)
外部コスト総額:200万円(求人広告費150万 + 紹介報酬50万)
内部コスト総額:100万円(担当者・面接官人件費)
採用人数:3人
200万円+100万円÷3人=100万円
この例の場合、一人を採用するために100万円のコストがかかっていることになります。
この数値を定期的に算出し、目標とする採用単価を設定することで、採用活動に関わるメンバー全員がコスト意識を持つことができ、効率的な活動につながります。
なぜ?採用コストが高騰してしまう3つの原因
具体的な削減策に進む前に、なぜ自社の採用コストが上がってしまうのか、その根本原因を理解することが重要です。原因が分かれば、より的確で効果的な対策をピンポイントで打つことができます。ここでは、多くの企業が直面している、採用コストが高騰してしまう3つの主要な原因を解説します。
1. 採用競争の激化による応募者不足
現在の日本は少子高齢化が急速に進んでおり、多くの業界で人手不足、すなわち「売り手市場」が深刻化しています。
この状況下では、一人の優秀な人材を多くの企業が奪い合う構図となり、採用競争が激化します。結果として、求人広告の掲載料や人材紹介会社への成功報酬(フィー)が市場全体で上昇し、これが外部コストを増加させる最も大きな要因となっています。特に人気職種や専門職種では、成功報酬が年収の35%を超えることも珍しくなく、コスト高騰の大きな原因となっています。
2. 採用チャネルのミスマッチ
「あの有名企業も使っているから」「とりあえず大手サイトに掲載しておけば安心だろう」という安易な理由で採用チャネルを選んでいませんか?
自社が本当に求めるターゲット層が利用していないチャネルに費用を投じても、効果的な応募は集まりません。例えば、「若手エンジニアを採用したいのに、事務職の転職希望者が中心のサイトに掲載する」といった典型的なミスマッチがこれにあたります。
費用対効果の低いチャネルへの投資は、応募単価を押し上げ、最終的な採用単価を不必要に高騰させる原因となります。
3. 早期離職による追加の採用発生
採用した人材が入社後1年や3年といった早い段階で離職してしまった場合、欠員補充のために再び最初から採用活動をやり直す必要が生じます。
これは、同じ採用コストが再度かかるだけでなく、離職者に支払った給与や、研修・教育にかかった内部コストもすべて無駄になることを意味します。目先の採用人数を追い求め、入社後の定着を見据えていない採用活動こそが、結果的に最も高くつく採用コストとなるのです。
採用コストを削減する具体的な10の方法
ここからは、採用コストを削減するための具体的な方法を10個、ご紹介します。
「外部コストの削減」「内部コストの削減」「採用の質向上(長期的なコスト削減)」の3つの観点から解説します。自社ですぐに始められるものがないか、ぜひ一つひとつチェックしながら読み進めてみてください。
1. 採用手法・求人媒体を見直す
現在利用している求人媒体や採用手法の費用対効果を、定期的に厳しく検証しましょう。
媒体ごとに「応募単価」や「採用単価」を算出し、最も効率的なチャネルを可視化します。効果が薄い媒体の出稿を停止したり、掲載プランをダウングレードしたりするだけで、大きな外部コスト削減につながります。
浮いた予算を最も効果の高い媒体に集中させることで、全体の採用パフォーマンス向上も期待できます。
2. ダイレクトリクルーティングを活用する
ダイレクトリクルーティングは、企業から候補者に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。
成功報酬型や安価な月額利用料のサービスが多く、人材紹介会社に支払う高額な成功報酬(フィー)よりも手数料を大幅に抑えられるケースが多いのがメリットです。さらに、自社の要件に合う人材をピンポイントで探してアプローチできるため、ミスマッチが起こりにくいという点も、長期的なコスト削減につながります。
3. 無料で使える採用チャネルをフル活用する
費用をかけずに母集団を形成できるチャネルは、可能な限りフル活用しましょう。
ハローワーク: 近年オンライン化が進み、以前よりも利便性が向上しています。掲載は無料ですが、丁寧な求人票を作成し、定期的に更新することが効果を出す鍵です。
大学のキャリアセンター: 地元の大学や専門学校のキャリアセンターとの連携は、新卒や第二新卒の優秀な学生に直接アプローチできる貴重な機会です。
4. 採用オウンドメディアやSNSで情報発信する
自社のブログ(オウンドメディア)やX(旧Twitter)、Instagram、FacebookといったSNSを活用し、会社の文化、働く社員の様子、事業のビジョンなどを継続的に発信しましょう。
これは「タレントプール」の構築につながります。すぐには効果が出ない施策ですが、中長期的に会社のファンを増やすことで、広告費に頼らず自然に応募者が集まる仕組みを構築できます。これは、最も効果的な中長期的な採用コスト削減策の一つです。
5. リファラル採用(社員紹介制度)を強化する
リファラル採用は、自社社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。
-
カルチャーフィットしやすい: 社員からの紹介であるため、入社後のミスマッチが少なく、定着率が非常に高い傾向にあります。
-
コストを大幅に抑制: 広告費や人材紹介手数料がかからず、インセンティブのみで採用できるため、コストを大幅に抑えることができます。
リファラル採用とは?そのメリット・デメリットと注意するべきこと
この制度活性化の鍵は、社員への周知徹底と納得感のあるインセンティブ設計です。
リファラル採用を成功させるインセンティブ設計のコツ
リファラル採用活性化には、社員のモチベーションを刺激する魅力的なインセンティブ制度が不可欠です。単なる金銭的報酬だけでなく、多角的な工夫が効果的です。
具体的な工夫の例:
金銭以外の報酬: 現金だけでなく、特別休暇の付与、旅行券や食事券の提供など、社員が喜ぶ多様な選択肢を用意する。
紹介プロセスでの評価: 採用に至らなくても、質の高い候補者を紹介してくれた社員を表彰するなど、「会社に貢献している」と実感できる仕組みを作る。
段階的な支払い: 「紹介時」「内定・入社時」「入社後半年経過時」など、インセンティブを分けて支給することで、社員の定着への意識も高める。
社員が「この制度を通じて会社に貢献したい」と心から思える制度にすることが、成功へのカギとなります。
6. 採用プロセスを効率化する
採用担当者や面接官の工数、すなわち内部コストの削減は非常に重要です。
-
一次面接のWeb面接への切り替え: 日程調整の手間を大幅に削減できるほか、応募者の交通費負担軽減、遠方からの応募者増加にもつながります。
-
採用管理システム(ATS)の導入: 応募者とのメール連絡、進捗管理、日程調整などの煩雑な事務作業を自動化し、担当者がコア業務(候補者との対話や戦略立案)に集中できる環境を整えます。
ハピキタで採用が変わる!北海道の人事担当者向け採用管理ツール徹底解説
7. 採用ピッチ資料を作成する
採用ピッチ資料は、候補者に向けて会社の魅力を構造的にまとめたプレゼン資料です。
事前に候補者へ共有することで、会社説明の手間を省き、面接ではより深い対話や質疑応答に時間を使えるようになります。候補者の企業理解が深まることで、選考中の意向醸成やミスマッチ防止につながり、結果として選考離脱や早期離職を防ぐという形でコスト削減に貢献します。
8. 求める人物像(ペルソナ)を明確にする
求める人物像が曖昧だと、選考基準がブレてしまい、無駄な面接が増えたり、入社後にミスマッチが起きたりします。
現場社員へのヒアリングを基に、スキル、経験、価値観、行動特性を具体的に定義した人物像(ペルソナ)を設定しましょう。採用に関わる全員が共通認識を持つことで、選考の精度が格段に上がります。
9. 選考基準を統一しミスマッチを防ぐ
求める人物像を明確にした後、次はそれを評価するための具体的な選考基準を設けます。
面接官による評価のバラつきを防ぐため、評価項目や質問内容を標準化した「面接評価シート」の用意が有効です。これにより、感覚的な採用から脱却し、客観的な基準で判断できるようになり、ミスマッチを大幅に減らすことができます。
10. 内定者フォローを手厚くし内定辞退を防ぐ
内定辞退が発生すると、それまでの求人広告費、面接官の人件費といった時間と費用がすべて無駄になってしまいます。
内定から入社までの期間、定期的な連絡(電話、メール)や、社員との懇親会、カジュアルなオフィス訪問などを企画し、内定者の不安解消と入社意欲の向上に努めましょう。内定辞退による欠員補充コストを防ぐことが、最後の重要なコスト削減策となります。
新卒採用のコスト削減で特に意識したいポイント
新卒採用は、中途採用と異なり、インターンシップや大規模な合同説明会、全国からの応募者の交通費など、特有のコストが発生します。ここでは、新卒採用の費用削減において特に効果的な3つのポイントを解説します。
1. オンライン説明会・面接を導入する
新卒採用で負担となりがちなコストとして、会場費、全国の学生の交通費、説明会資料の印刷費、担当者の出張費などがあります。
これらをオンラインに切り替えることで、物理的なコストを大幅に削減できます。さらに、地方在住の学生も時間や費用の負担なく参加しやすくなり、これまで出会えなかった優秀な人材にアプローチできるという、母集団形成のメリットも同時に享受できます。
2. インターンシップから採用につなげる
インターンシップは、学生に実際の業務や社風を体験してもらう絶好の機会です。
学生は企業理解を深められ、企業側は学生の能力や人柄をじっくり見極められるという、採用におけるミスマッチを最小限に抑える双方のメリットがあります。インターンシップ経由で優秀な学生に早期内定を出せれば、大規模な広報費やイベント出展費をかけずに、採用目標を効率的に達成できる可能性が高まります。
3. 大学のキャリアセンターとの連携を強化する
自社が求める人材像に合った大学や学部のキャリアセンターと、日ごろから良好な関係を築くことは、低コストで質の高い母集団を形成する上で非常に重要です。
信頼関係を構築することで、学内説明会への優先参加や、推薦枠、優秀な学生の直接紹介といった貴重なメリットが得られる可能性があります。求人サイトだけに頼らない、地道で丁寧な連携こそが、効率的かつ低コストな新卒採用につながります。
北海道の中小企業が新卒採用で成功するためにできること。「ジョブキタ就活」で通年採用
採用コスト削減で失敗しないための3つの注意点
コスト削減は重要ですが、やり方を間違えると、かえって採用の質を低下させ、将来的な損失を招くリスクがあります。
そこで、コスト削減に取り組む上で絶対に押さえておきたい3つの注意点を解説します。
1. 必要なコストまで削って採用の質を落とさない
コスト削減を意識するあまり、必要な投資まで削るのは本末転倒です。例えば、
採用担当者が多忙で応募者への連絡が遅れ、離脱が増える。
面接時の交通費支給を辞め、優秀な遠方からの候補者を逃す。
適性検査を辞めてしまい、ミスマッチ人材を採用してしまう。
などは、目先の費用は削れても、最終的に大きな損失を招きます。闇雲に費用を削るのではなく「削減すべきコスト(ムダ)」と「投資すべきコスト(質向上)」を戦略的に見極める視点を持つことが重要です。
2. 長期的な視点で費用対効果を判断する
採用オウンドメディア、リファラル採用、企業ブランディングなどは、すぐに結果が出ない施策です。しかし、これらの施策は、一度軌道に乗れば、将来にわたって大きなコスト削減効果と質の高い採用をもたらす「企業資産となります。
目先の広告費(外部コスト)だけでなく、入社後の定着率や活躍度まで含めた、長期的な視点で費用対効果を判断することが不可欠です。短期的な結果に囚われず、将来の「採用力」につながる施策への投資は継続しましょう。
3. 削減したコストを別の重要施策に再投資する
コスト削減の目的は、単に経費を浮かせることだけではありません。
削減で生まれた予算を、社員の教育研修や福利厚生の改善、エンゲージメント向上施策など、社員の定着率や満足度を高める施策に再投資することを提案します。
これにより、「採用しやすく、辞めにくい」という好循環が生まれ、企業全体の成長につながります。コスト削減を「守り」で終わらせず、強い組織を作るための「攻め」の戦略へと転換させることが、最も賢明なコスト削減戦略です。
まとめ:自社に合ったコスト削減で、北海道での採用を成功させよう
本記事では、採用コストの内訳から、コストが高騰する根本原因、そして自社ですぐに始められる具体的な削減方法10選、さらには失敗しないための注意点までを解説しました。
採用コストの削減は、単なる経理的な作業ではなく、自社の採用活動全体を見直し、長期的な採用力を強化するための戦略そのものです。まずは一つでも、自社で始めやすいものから着手し、その効果を測定しながら継続的に改善していくことが、持続可能な採用力の強化につながります。
北海道での採用課題は、北海道アルバイト情報社(HAJ)にご相談を
「どの採用手法が自社に合っているかわからない」「北海道の採用市場に合った最適な戦略を知りたい」といった課題をお持ちであれば、ぜひご相談ください。
北海道の採用市場を熟知した北海道アルバイト情報社(HAJ)は、企業の採用課題に合わせた最適なプランを提案し、企業の採用成功をサポートします。
コスト削減の第一歩である「採用手法・求人媒体の見直し」から、専門家の視点で最適な媒体選定や求人原稿の改善をサポートし、費用対効果を最大化するお手伝いが可能です。
アルバイトから正社員まで。多様なニーズに応える「アルキタ」「ジョブキタ」
HAJが提供する具体的なサービスとして、北海道のアルバイト採用に強い「アルキタ」と、正社員・契約社員採用に特化した「ジョブキタ」があります。
アルバイト採用から中途採用まで、企業の多様な採用ニーズにワンストップで応えることが可能です。
本記事でご紹介したような採用コストの最適化を実現するため、まずは現在の課題や予算について、お気軽にHAJにご相談ください。北海道の企業様の「攻め」と「守り」の両輪の採用戦略を、強力にサポートいたします。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂 智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。