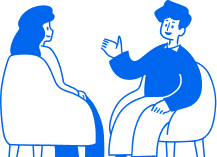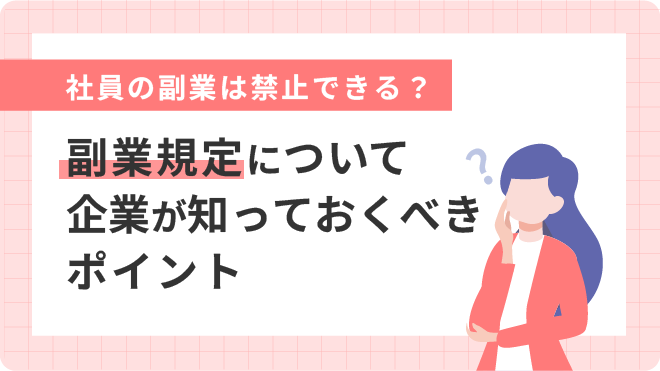
企業の働き方が多様化する現代において、社員の副業・兼業への関心が高まっています。社員から副業の相談を受け、「どこまで認めるべきか」「そもそも会社として禁止することは可能なのか」といった疑問を抱えているご担当者も少なくないでしょう。
この記事では、企業が社員の副業について法的な側面から知っておくべきポイントと、時代に合わせた副業規定のあり方について解説します。
目次
副業・兼業を禁止できるのは「正当な理由」がある場合のみ
まず、法的な側面から見ていきましょう。労働基準法には、副業や兼業を直接的に禁止する規定はありません。むしろ、憲法で保障されている「職業選択の自由」との兼ね合いから、本業の労働時間外であれば副業を行うことは個人の自由であると考えられています。この原則は、労働者が自らのキャリアやライフスタイルを主体的に選択する権利を尊重するものです。
しかし、多くの企業が就業規則で副業を禁止しているのも事実です。これは、企業として「正当な利益」を保護する目的がある場合に限り、副業禁止が認められるためです。
「正当な理由」に該当する4つケース
具体的には、以下のような要素が、企業が副業を制限する正当な理由として該当します。
- 本業の働きぶりに支障が生じる場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉・信用を毀損するおそれがある場合
- 競業により企業の利益を害する場合
それではこの4つの理由について解説していきます。
1.本業の働きぶりに支障が生じる場合
単なる疲労ではなく、副業による過労が原因で、本業での集中力が著しく低下したり、業務効率が著しく落ちるなど、会社の生産性に直接的な悪影響を及ぼすケースです。過度な長時間労働を伴う副業も、この点から問題視される可能性があります。
2.企業秘密が漏洩する場合
自社の顧客情報、開発中の技術、未公開の経営計画といった機密情報やノウハウを、副業先で不正に利用したり、意図せずとも漏洩させてしまうリスクがある場合です。これは会社の競争力を根底から揺るがす深刻な事態につながりかねません。
3.会社の名誉・信用を毀損するおそれがある場合
副業の内容が、社会的に不適切であったり、企業のブランドイメージや信頼を著しく損なうような場合です。例えば、公序良俗に反するような活動や、会社の社会的責任を問われるような行為がこれにあたります。社員の副業が会社の顔として見なされる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
4.競業により企業の利益を害する場合
副業が、自社の事業と直接的に競合し、売上や顧客を奪うなど、会社の正当な利益を直接的に侵害するケースです。特に、同業他社での副業や、類似のサービスを個人で提供する副業は、会社の利益保護の観点から制限される可能性が高いといえます。
政府も推進する「副業・兼業」の流れ
正当な理由があれば副業・兼業を禁止することは可能であることを前段ではお伝えしましたが、近年、副業は労働者にとって当たり前の選択肢となりつつあります。政府もこの動きを後押ししており、厚生労働省が公表する「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、2018年1月にモデル就業規則を改定。「許可なく他の会社などの業務に従事しないこと」という文言を削除し、「労働者は、所定労働時間以外の時間において、他の会社等の業務に従事することができる」と明記されました。
これは、労働者の多様なキャリア形成や自己実現を支援する目的から、副業・兼業を原則として容認する方向へと企業に促すものです。実際に、総務省の就業構造基本調査によれば、副業者数は2012年の234万人から2022年には332万人にまで増加しており、この10年間で約4割増という顕著なトレンドが全国的に見られます。
北海道における副業・兼業の広がりと企業の動き
北海道でもこの潮流は広がりを見せており、特に人手不足に悩む中小企業にとって、副業・兼業人材の活用は重要な課題解決策となりつつあります。道内企業における外部人材の活用支援は積極的に行われており、経済産業省北海道経済産業局の取り組みからもその姿勢がうかがえます。
例えば、「副業・兼業人材活用促進補助金」といった制度が設けられるほか、道内の食品製造業がEC戦略の専門家を副業人材として迎え入れ、売上拡大につなげた事例も報告されています。このような外部の専門人材を活用することは、企業にとって新たなノウハウや視点を取り入れる機会となり、結果として競争力強化につながることが期待されます。道内の企業は、こうした外部の力を取り入れることで、地域経済の活性化にも貢献していくことが求められています。
副業が企業にもたらす4つのメリット
情報漏洩や本業への影響といった懸念はあるものの、開かれた権利となりつつある副業・兼業を慣習的に禁止することは、時代に逆行してしまう可能性があります。
また、社員の副業・兼業自体が企業側にはデメリットばかりと思いがちですが、企業にとってもメリットがあります。
- 社員のスキルアップと生産性向上
- エンゲージメントの向上と離職防止
- 多様な人材の確保
- 企業ブランドイメージの向上
それでは、この4つのメリットについて解説します。
1.社員のスキルアップと生産性向上
副業は、社員が本業とは異なる分野や環境で新たなスキルや知識、経験を習得する絶好の機会です。そこで培われたスキルやネットワーク、知見が本業に還元されることで、個人だけでなく、組織全体の生産性向上やイノベーションの創出につながる可能性があります。
2.エンゲージメントの向上と離職防止
やりたいことに挑戦できる自由な環境は、社員の仕事に対するモチベーションや会社へのエンゲージメントを大きく高めます。自分のキャリアを主体的に形成できるという実感は、社員の満足度を向上させ、結果的に離職率の低下にも寄与すると考えられます。
3.多様な人材の確保
柔軟な働き方を認める企業は、転職を検討している優秀な人材にとって魅力的に映ります。多様なバックグラウンドを持つ人材を引きつける要素となり、結果として企業の組織風土を豊かにし、新たな価値観を生み出す源泉となります。
4.企業ブランドイメージの向上
社員の主体的なキャリア形成に寛容な姿勢を示すことは、社会からの信頼獲得や採用市場における企業ブランドの向上にもつながります。これは、単なる福利厚生ではなく、企業が社員の成長を本気で支援するというメッセージとなり、社会からの評価を高めることになります。
副業規定を策定するための具体的な6つのフロー
時代の流れで副業や兼業が広まりつつある中で、現在副業を禁止している企業の担当者の方の中にも、「なぜダメなのか」と社員から言われた経験もあるのではないでしょうか。
そういった場合には慣習的に副業を禁止するのではなく、社員と対話を重ねて「なぜダメなのか」という理由を具体的に掘り下げることが重要です。その上で、企業として許容できる「OKライン」はどこにあるのか、明確なルールを定めていく必要があります。
では、実際に副業を容認する方向でルールを定めていく場合、どのようなステップを踏めばよいのか。以下の5つのフローで解説します。
- 現状把握と目的の明確化
- 就業規則の見直し
- 許可基準の策定
- 申請・報告手続きの整備
- 情報セキュリティ対策の強化
- 社員への周知と対話
1.現状把握と目的の明確化
まず、自社の社員が副業に対してどのような関心を持っているか、アンケートやヒアリングを通して現状を把握します。その上で、副業を認めることの目的(人材確保、社員のスキルアップ促進など)を経営層や人事部門で明確に共有します。
2.就業規則の見直し
現行の就業規則で副業禁止規定がある場合、これをどう変更するかを検討します。「原則容認」とするか、リスク管理のために「許可制」とするか、自社の事業内容や風土に合わせて具体的なルールを話し合います。
3.許可基準の策定
副業を「許可制」にする場合、許可する・しないの明確な基準を設けます。
例:競業にあたる副業は禁止、本業に支障が出ない範囲での労働時間(週〇時間以内など)、情報漏洩リスクがないこと、など。
4.申請・報告手続きの整備
社員が副業を始める際の申請方法や、年間の活動状況を報告する仕組みを定めます。申請書には、副業の内容、期間、労働時間、報酬などを具体的に記載させ、会社が状況を把握し、社員への適切なアドバイスや支援につなげられるようにします。
5.情報セキュリティ対策の強化
副業によって企業秘密が漏洩するリスクに備え、情報セキュリティに関する教育を改めて実施したり、副業先で機密情報を扱わない旨の誓約書を取り交わすなどの対策を検討します。
6.社員への周知と対話
新しい副業規定を策定したら、全社員にその内容を周知します。単なる通達ではなく、説明会や質疑応答の場を設けることで、社員の疑問や不安を解消し、円滑な運用を目指します。
まとめ:副業に対する考え方のシフトが、今後の企業成長や社員の離職防止・人材確保における重要な鍵
この記事では、社員の副業・兼業を禁止できるか、について解説しました。禁止できるのは、正当な理由がある場合のみで、近年は政府も副業を推進し、全国的に副業者数が増加しています。企業にとっても、社員のスキルアップやエンゲージメント向上、多様な人材確保、企業ブランド向上などのメリットがあるため、副業に対する考え方を「禁止」から「活用」へとシフトしていくことが、今後の企業成長や社員の離職防止・人材確保における重要な鍵となるかもしれません。ぜひ、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。