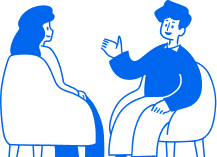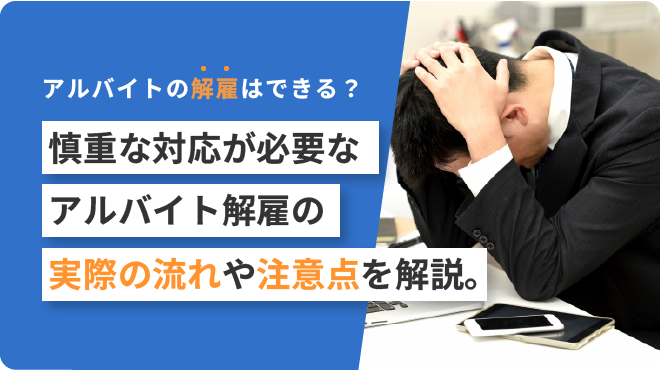
業務のパフォーマンスが低かったり、勤務態度に問題があったりするアルバイトがいる場合、解雇を検討するケースがあるかもしれません。しかし、前述の理由で実際に解雇しトラブル(訴訟)となった場合は、ほとんど企業側が敗訴しているケースが多いのが現状です。
この記事では、アルバイトを解雇できるかどうかに加え、解雇を検討するべきケース、不当解雇のリスク、具体的な解雇の流れや注意点などを解説します。アルバイトの解雇にお悩みの人事担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
【結論】アルバイトの解雇は条件が揃った場合のみ
アルバイトを解雇することは可能ですが、アルバイトも正社員と同様に労働契約法等が適用されるため、簡単に解雇できるわけではありません。
解雇を行う場合は、客観的に誰もが認めるような合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる正当性があることを証明しつつ実施する必要があります。正当性が認められないと、不当な解雇とみなされ、解雇が無効になる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
アルバイトの解雇の正当性が認められるケース
アルバイトの解雇が認められるのは、以下の4つのケースです。不当解雇とならないよう、これらのケースを理解しておくことが重要です。
- 就業規則の解雇事由に該当する(規定内容に合理性等があるかの確認が必要)
- バイトテロなど企業に悪影響を与える行為があった
- 不正行為が発覚した
- 倒産レベルの経営不振により整理解雇する必要があった
アルバイトの解雇を検討する際は、これらの点を必ず確認しましょう。
1.就業規則の解雇事由に該当する
就業規則とは、労働時間・賃金・服務規律など、従業員が働く上で守るべきルールや労働条件を定めたものです。無断欠勤の繰り返しや業務命令への重大な違反など、解雇事由を就業規則に記載することも可能です。就業規則に記載された解雇事由に従業員の行為が該当する場合は、従業員を解雇する正当な理由となります。より正当性を高めるために、就業規則が従業員に周知されていること、そして規則の運用が客観的かつ合理的に行われていることが重要です。
2.バイトテロなど企業に悪影響を与える行為があった
バイトテロとは、アルバイト従業員がSNSなどに不適切な投稿を行い、企業のブランドイメージや信用を著しく毀損する行為を指します。バイトテロは、企業の営業活動に大きな影響を与え、顧客離れや売上減少につながる可能性があります。企業に重大な損害を与えたり、社会的な信用を失墜させたりした場合、解雇の正当性が認められるケースとなります。ただし、当該行為が企業に与えた影響の大きさや、事前の指導・注意の有無などから、解雇の正当性を総合的に判断する必要があります。
3.不正行為が発覚した
不正行為とは、横領や窃盗、情報漏洩など刑事法上罰せられ得る行為を指します。不正行為は、企業に直接的な財産的損害を与えるだけでなく、企業の信用をも失墜させます。不正行為を行った従業員は、解雇の正当性が認められる可能性があります。事実関係を正確に把握し、不正行為がされた証拠を揃えることで、解雇の正当性を立証しやすいでしょう。
4.経営不振により整理解雇する必要があった
整理解雇とは、企業の経営不振などにより事業規模を縮小せざるを得ない場合に、人員削減を目的として行われる解雇であり、いわゆるリストラを指します。先ほどの3つのケースに比べて、整理解雇の場合はより正当性を慎重に検討する必要があります。
整理解雇の正当性が認められるためには、以下の4つの要件を満たすことが大切です。
- 「整理解雇」の必要性があること
- 解雇を回避するための努力をしたこと
- 解雇の対象者の選定基準が客観的合理的であること
- 必要性・時期・基準について従業員に説明し協議を尽くしたこと
整理解雇を行う際は、上記の4つを満たすように慎重に進める必要があります。ただし、この4つの要件が揃っていても、企業経営が倒産レベルでない限り、成立していない判例がほとんどです。
アルバイトの不当解雇にあたる例
アルバイトの解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は不当解雇とみなされます。不当解雇に当たる例として、以下が挙げられます。
- 業務のパフォーマンスが不足している
- 協調性や勤務態度に問題があった
- 業務を進めるうえでのスキルが不足している
- 遅刻等の就業規則違反などを数回している
指導や教育で改善できる能力不足や問題行動は、それだけでは解雇の正当性が認められません。上記のようなケースは、解雇の前に改善の機会を与えたり、配置転換を検討したりするなど、解雇以外の手段を講じる努力が求められます。
また、上記のようなケースに当てはめても、会社での評価と裁判所等での評価が異なり、採用した企業にも責任があるとみなされるケースもあります。このようなケースでは企業側からの一方的意思表示である【解雇】ではなく、【契約解除】という考えを使い、当該労働者に対し本音で説得し、雇用契約を合意の上で解約する方法が望ましいでしょう。
アルバイトを不当解雇した場合のリスク
ここからは、アルバイトを不当解雇した場合のリスクについて、以下の2つの点を解説します。リスクを理解することで、不当解雇を回避するための慎重な判断と、適切な対応の重要性を認識できるでしょう。アルバイトの解雇を検討している方は一度確認しましょう。
企業のブランドイメージが低下する可能性がある
アルバイトを解雇した後、従業員が訴訟を起こして不当解雇とみなされることで、解雇が無効と判断されるケースが多くあります。企業側が裁判で敗訴することで、不当解雇したことが世間に伝わり、企業のブランドイメージが低下する可能性があります。ブランドイメージが低下すると、顧客や取引先からの印象が悪くなり、売り上げに悪影響を及ぼしやすいです。
また、優秀な人材の確保が困難になることで、競争力が下がるリスクもあります。さらに、退職後にSNS転職サイト等にパワハラなども付け加えられて退職者から投稿されたり、リベンジ退職されてしまう、といった問題に発展する可能性もあります。
アルバイトが働いていない期間の賃金の支払いが発生する
不当解雇の場合、裁判等で敗訴すると従業員を解雇しても無効になるため、働いていなかった期間も雇用契約が継続しているとみなされます。そのため、解雇された日から実際に復職するまでの期間の賃金をまとめて支払う義務が生じます。従業員が働いていない期間が長ければ長くなるほど、遅延利息なども発生し支払う金額が高額になり、企業の財政に大きな負担となる可能性があります。売り上げによっては、経営状態が傾くきっかけになりかねません。
アルバイトを解雇する際の流れ
ここからは、アルバイトを解雇する際の流れを、以下の4つのステップに分けて解説します。あらかじめ流れを理解することで、解雇をスムーズに、正しい形で実行できるでしょう。アルバイトを解雇する予定の方はぜひ確認しておきましょう。
- 解雇しても問題ないか検討する
- 解雇の準備を行う
- 解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いを行う
- 解雇後の必要な手続きを行う
1.解雇しても問題ないか検討する
アルバイトが就業規則に抵触したり、不正行為が見られたりした場合は、まず内容を十分に確認します。企業への被害が甚大であり、解雇が検討される場合は、不当解雇に当たらないか改めて確認しましょう。先ほど紹介した「解雇の正当性が認められるケース」を確認し、労働者から訴えられる余地がないかを考えます。経営層・専門家を交えて複数人で相談し、慎重に判断することを心がけましょう。また、立証できる十分な証拠が必要です。
2.解雇の準備を行う
解雇が決定したら、準備段階として、解雇が正当であることを証明する証拠を揃えます。バイトテロや不正行為によって売り上げに影響が出た場合は、問題行動の記録や、影響の内容がわかる資料を準備します。整理解雇の場合は、解雇の対象者や正当性などを議論した議事録をまとめておきましょう。
また、解雇する旨と解雇日を明記した解雇予告通知書もあらかじめ作成します。なお、解雇は原則として30日前までに予告しなければならない旨が定められています。解雇を通知してから30日以内に解雇する場合、30日に足りない日数分、解雇予告手当の支払いが必要です。バイオテロなどですぐに解雇する必要がある場合は、解雇予告手当の計算も事前に行いましょう。(労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けた場合は必要なく、内容調査などにより認定が後日となった場合は、返還請求出来る場合もあります。)
【補足】解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当は、原則として「支払う日数分の平均賃金額」となります。平均賃金は、原則として解雇予告日の前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数で割って求めます。
ただし、日給制や時給制のアルバイトの場合、上記の計算方法で算出した平均賃金が、総賃金額を労働日数で除した額の60%に満たない場合は、後者の額を最低保障額として適用します。
解雇予告手当の計算を間違えると、適切な額を支払えないことで、法的な問題に発展する可能性もあるため、最低保障額の計算も含めて、やり方をよく確認しながら進めましょう。
3.解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いを行う
解雇の準備が整ったら、対象のアルバイトに対して解雇の通知を行います。解雇予告通知書を渡すほか、解雇予告手当を支払う場合は、解雇の通知と同時に支払いを実施しましょう。解雇はデリケートな話題であるため、アルバイトと話せる日時を打ち合わせて、1対1で話せる場を作ったうえで伝えることが大切です。
4.解雇後の必要な手続きを行う
アルバイトを解雇した後、労働保険や社会保険などに関する手続きを行う必要があります。手続きの例としては以下の通りです。
- ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届や離職証明書を提出する
- 年金事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する
- 「給与支払報告に係る給与所得異動届書」を従業員が居住する市町村に提出する
上記のような手続きは、アルバイトに限らず従業員が離職した際に対応が必要です。手続きを怠ると、企業が行政指導や罰則の対象となる可能性もあるため、細心の注意を払って対応しましょう。
アルバイトを解雇する際の注意点
ここからは、アルバイトを解雇する際の注意点として、以下の2点を解説します。注意点を押さえることで、解雇を行う際にトラブルが起きにくくなります。企業の人事担当の方は、アルバイトの解雇に備えて一度確認しておきましょう。
- 解雇する前に指導できる余地がないか検討する
- 有期雇用契約の場合は雇止めも検討する
解雇する前に指導できる余地がないか検討する
アルバイトを安易に解雇することは、企業にとって人材不足や採用コスト増大のリスクを招く可能性があります。そのため、問題行動が見られた場合でも、まず指導や教育によって改善できる余地がないかを十分に検討しましょう。
業務上のミスや勤務態度不良に対しては、具体的な改善策を提示し、期限を設けて指導を行うことが重要です。バイトテロや不正行為など重大な事態に対しては、減給をはじめとする懲戒処分を検討するのも一つの手です。減給の条件は労働基準法で定められており、1回の減給額は平均賃金1日分の半分以下、また複数回減給を行う場合の減給の総額は、1賃金支払い期の賃金の10分の1以下である必要があるため注意しましょう。
指導や懲戒処分を経てなお改善が見られない場合に、解雇を検討するという段階を踏むことで、より解雇の正当性を高められます。
有期雇用契約の場合は雇止めも検討する
雇止めとは、期間の定めのある労働契約が期間満了により終了することで、アルバイトの雇用を終えることを指します。有期雇用契約のアルバイトの場合、契約期間満了をもって契約を更新しない「雇止め」も、解雇とは異なる選択肢として検討できます。
ただし、契約更新が繰り返され、実質的に期間の定めのない契約とみなされる場合や、同様の業務を行っている別の労働者を雇用継続等する場合は、雇止めが適用されないケースもあります。また、一部のケースを除き、雇止めの場合も30日前までに予告が必要であるため注意しましょう。
アルバイトの解雇に関するよくある質問
ここからは、アルバイトの解雇に関するよくある質問として、以下の2点を解説します。よくある質問とその回答を確認することで、アルバイトの解雇について、細かい点まで把握できます。アルバイトを採用している企業の人事担当者はぜひ確認しましょう。
Q.アルバイトは試用期間でも解雇できる?
A.アルバイトは試用期間中であっても解雇は可能です。ただし、本採用後の解雇と同様に客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要となります。
また、アルバイト本人にとっては入社直後に解雇される事態であるため、精神的な負担を考慮して慎重かつ丁寧に伝えるよう心がけましょう。なお、入社日から14日以内の試用期間中の解雇であれば、解雇予告手当の支払いは不要とされています。
Q.アルバイトの解雇に退職金は必要?
A.アルバイトを解雇する際に退職金を支払う必要がある旨は、労働基準法をはじめとする日本の法律で定められていません。そのため、アルバイトを解雇する際に退職金を支払わなくても、特に法的な問題はありません。
ただ、企業が就業規則や労働契約において退職金制度を設けており、その適用対象にアルバイト従業員が含まれる場合は支払いが必要です。企業独自の制度には従うことを心がけましょう。また、合意解約などの場合には、相手にも言い分がある場合があるため、退職金として金銭解決する方法もあります。
まとめ:アルバイトを解雇するかは慎重に判断を
アルバイトを解雇する際は、正社員と同様に誰もが認める客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性、そして立証できる証拠等が不可欠です。不当解雇と判断された場合、未払い賃金の支払い義務や企業のブランドイメージ低下など、企業にとって大きなリスクがあります。
解雇を検討する際は、就業規則の解雇事由への該当や不正行為など、正当性が認められるケースに当てはまるかを慎重に判断しましょう。また、30日前までの解雇予告や解雇予告手当など、実際に解雇を行う際のルールもあらかじめ把握しておきましょう。

Writer
ヒトキタ編集部 小林陽可
Profile
求人営業部での法人営業を経験した後、WEB記事のライティングや自治体への移住施策企画のディレクション等に従事。現在は広報業務・営業支援を行う。