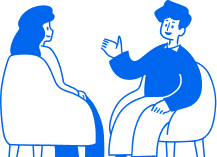企業が従業員を守る姿勢は、求職者には職場の魅力として伝わりやすい要素の一つです。特に、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応は、企業の真価を問われる時代。北海道では2025年4月に全国初のカスハラ防止条例が施行されました。
従業員を守るための対策は、採用市場における強力な武器。この記事では、カスハラが増えている背景や企業が取るべきカスハラ対策、さらに企業の成功事例について解説します。
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?
カスハラとは、顧客や取引先からのハラスメント行為全般のこと。具体的には、以下のような行為が該当します。
- 暴言・脅迫:大声で怒鳴る、侮辱的な言葉を浴びせる、脅迫的な言動をとる
- 暴力:殴る、蹴る、物を投げつける
- セクハラ:性的な冗談を言う、体を触る、性的な関係を迫る
- 不当な要求:サービス内容を超える要求をする、執拗にクレームをつける
- 差別:人種、性別、年齢、障害などを理由に差別的な言動をとる
カスハラが従業員に与える影響は大きく、精神的な苦痛だけでなく、不眠や頭痛、腹痛といった身体的な不調、仕事の意欲の低下、さらには離職にもつながりかねません。
カスハラが増えている背景
ある調査では、顧客折衝のあるサービス業に従事する人のうち、3割強の人はカスハラの被害経験があるという結果も出ています。カスハラの被害の背景には、以下のような複数の要因が挙げられますが、これらの要因が複合的に絡み合うことで、カスハラ被害はさらに増えていると考えられています。
1.社会の変化と価値観の多様化
- 偽装表示や欠陥商品など企業の不祥事を伝えるニュースから、消費者が商品やサービスに過剰な不安や不信感を抱くようになった。
- インターネットやSNSの普及により、個人の意見や不満が拡散しやすく、企業や従業員に対する批判や攻撃がエスカレートする傾向がある。
2.顧客意識の変化
- 顧客意識が向上し、サービスに対する要求水準が高まっている。それ自体は良いことだが、それが過剰な要求や理不尽なクレームにつながる場合も。
- 日本はおもてなし精神を美徳とし、「お客様は神様」という言葉もある。これが顧客の権利意識を過剰に高め、従業員への横柄な態度やハラスメントにつながるケースも考えられる。
3.労働環境の変化
- 人手不足や業務の多忙化により、従業員が精神的に余裕がなくなり、顧客からのクレームや要求に対して過剰に反応してしまう可能性も。
カスハラ対策3つのステップ
カスハラ対策は自社の従業員を守るという観点から、企業が組織全体で取り組む必要があります。以下の3つのステップに沿って、具体的な対策を講じましょう。
ステップ1:予防策を講じる
カスハラは、発生を未然に防ぐことが最も重要です。
- 社内ルールの策定と周知:どのような行為がカスハラにあたるのか、明確な基準を定めます。不当な要求には応じない、担当者変更を申し出るなど、従業員が判断に迷わないための具体的な対応方針を社内規定に盛り込み、周知徹底します。
- 従業員教育の実施:カスハラに関する研修を実施し、従業員が正しい知識と対応スキルを身につけられるようにします。ロールプレイング形式で実践的な対応を学ぶのも有効です。
- 顧客への情報発信:Webサイトやサービス利用規約に「カスハラ行為には毅然と対応する」旨を明記します。これにより、カスハラ行為をけん制する効果が期待できます。
ステップ2:発生時の対応体制を整備する
カスハラが発生してしまった場合、迅速かつ適切に対応できる体制を整えます。
- 相談窓口の設置:従業員が安心して相談できる窓口を設けます。社内の専門部署や外部の専門家と連携することも有効です。相談内容の秘密保持を徹底し、従業員のプライバシーを守ります。
- 対応フローの確立:カスハラが発生した場合の具体的な対応フローを定めます。初期対応からエスカレーション、警察との連携まで、誰が何をするのかを明確にし、従業員が一人で抱え込まない仕組みを作ります。
- 証拠の記録:カスハラ行為の証拠を記録します。日時、場所、言動、周囲の状況などを詳細に記録することで、後の法的措置や社内調査に役立ちます。
ステップ3:従業員のメンタルケアを徹底する
カスハラ被害は、従業員の心に大きな傷を残す可能性があります。
- 専門家との連携:産業医やカウンセラーなど、専門家と連携して、カスハラ被害を受けた従業員がいつでも相談できる体制を整えます。
- 休職・配置転換制度の整備:必要に応じて、従業員が安心して療養できる休職制度や、ストレスの原因から離れるための配置転換制度を整備します。
カスハラ対策の成功事例
事例1:小売業A社
A社は、お客様相談窓口に寄せられた過去のクレーム事例を分析。その結果、特定の時間帯や曜日、特定の従業員に対して、クレームが集中していることが判明しました。そこで、以下のような対策を実施しました。
- クレームが集中する時間帯に、経験豊富な従業員を配置
- 特定の従業員に対して、接遇研修を実施
- お客様相談窓口の受付時間を延長
事例2:飲食店B社
B社では、お客様からの理不尽な要求や暴言が頻発しており、従業員の精神的な疲労が問題となっていました。そこで、以下のような対策を実施しました。
- カスハラ対策に関する研修を実施
- 理不尽な要求に対しては、毅然とした態度で対応するよう従業員に指導
- 必要に応じて、警察に通報するなどの対応も辞さないことを周知
これらの対策により、従業員は安心して働けるようになり、顧客からの理不尽な要求も減少しました。
カスハラは、従業員個人の問題ではなく、企業全体の責任として捉える必要があります。求職者は、企業がどのようなカスハラ対策をしているのか、その職場は安心して働ける環境なのかどうか等を事前に知っておきたいと考えています。
採用活動時の求人広告や面接等の場面で、カスハラ対策に関する企業の取り組みを説明すれば、求職者に安心感を与えることにもなり、それが応募や後々には従業員の定着にもつながるはずです。

Writer
ヒトキタ編集部 友坂智奈
Profile
法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。